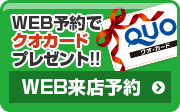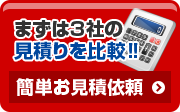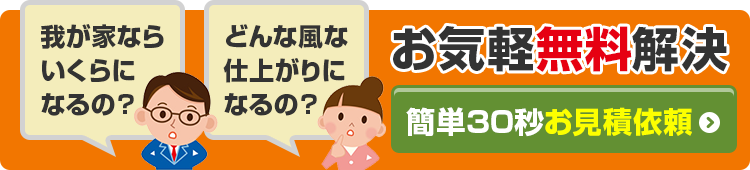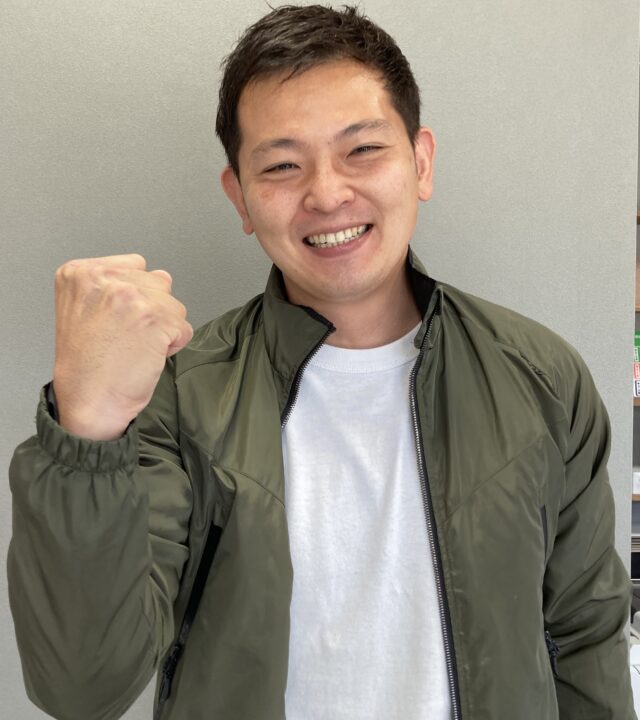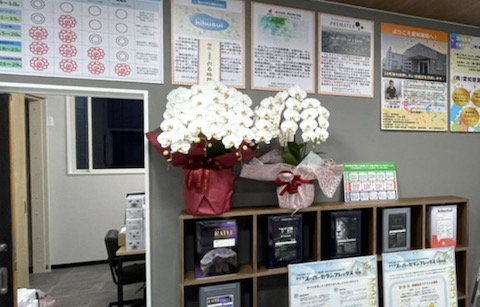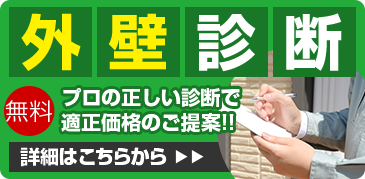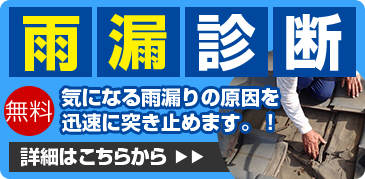塗料の種類に注目!!
2025.09.23 (Tue) 更新
今回は塗料の種類に注目して説明します!!
目次
①アクリル塗料
アクリル塗料とは、合成樹脂であるアクリル樹脂を主成分とする塗料で、外壁塗装の分野で最も歴史の古い塗料の一つです。かつては主流でしたが、現在ではシリコン塗料やフッ素塗料に置き換えられることが多くなりました。
1.特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 価格が安価 | 外壁塗装用塗料の中で最も安い部類。 |
| ✅ 発色が良い | 色の出方が鮮やかで、見た目が美しい。 |
| ✅ 乾燥が早い | 作業効率が良く、DIYにも向いている。 |
| ❌ 耐久性が低い | 寿命は3〜5年程度。再塗装の頻度が高い。 |
| ❌ 紫外線に弱い | 色あせ・ひび割れが早期に起きやすい。 |
| ❌ 汚れやすい | 防汚性や防カビ・防藻性能は高くない。 |
2. アクリル塗料はどんな場面に使う?
現在の住宅外壁ではあまり使用されなくなってきましたが、以下のような場面では選ばれることもあります。
-
とにかく低予算で済ませたい場合
-
仮設住宅・短期的な建物
-
DIY塗装
3.プロの塗装業者がアクリルを使うことはある?
基本的には「一般住宅の外壁」には使用しません。ただし、古い建物の一時的な美観向上や、予算が限られている物件などで採用される場合もあります。最近では「水性アクリル塗料」の開発が進み、室内や下塗り用としての利用もあります。
結論
アクリル塗料は「低価格で手軽」というメリットがある一方、「短命で汚れやすい」というデメリットがあるため、外壁に長期使用するには不向きです。
ただし、予算が限られている/短期間だけ見た目を改善したいなどのケースでは検討の余地があります。
②ウレタン塗料
ウレタン塗料とは、ウレタン樹脂(ポリウレタン)を主成分とする塗料で、外壁塗装において長年使われてきた信頼ある塗料です。かつては主流でしたが、近年ではシリコン塗料に主役の座を譲りつつあります。
それでも「適度な耐久性」と「柔軟性」「コスト面のバランス」で、今でも一定の人気があります。
1. ウレタン塗料の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 価格が手頃 | シリコンより安く、アクリルよりやや高い中間的価格帯。 |
| ✅ 密着性が良い | 細かい部分や木部・鉄部にもよく密着する。 |
| ✅ 柔軟性あり | 弾性があり、ヒビ割れに強い傾向。 |
| ❌ 耐久性はそこそこ | 耐用年数は約5〜8年程度。シリコンには及ばない。 |
| ❌ 汚れやすい | 防汚性や防カビ性は中程度で、年数が経つと艶が引けやすい。 |
2. ウレタン塗料の耐用年数とメンテナンス
-
耐用年数:5〜8年
-
おすすめメンテ周期:7年前後で再塗装を検討
-
劣化症状:艶落ち、チョーキング、ひび割れ、剥がれなどが起こりやすくなる
3. 他の塗料との比較(価格と耐久)
| 塗料種類 | 耐用年数 | 価格感 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アクリル | 3〜5年 | ◎ 非常に安い | 古いタイプ、短命 |
| ウレタン | 5〜8年 | ○ 安価 | 柔軟性あり、密着力あり |
| シリコン | 8〜12年 | △ 中価格 | 現在の主流 |
| フッ素 | 12〜15年 | ✕ 高価格 | 高耐久、撥水性良好 |
| 無機 | 15〜20年 | ✕✕ 非常に高価 | 耐久・防汚性抜群 |
4. ウレタン塗料の向いているケース
-
木部・鉄部など複雑な素材が多い場所
-
短期的に費用を抑えたいとき
-
部分補修・下地補修を中心とする施工
-
マンションの鉄階段・手すり等の補修塗装
5. プロ業者はウレタンをいつ使う?
最近では外壁全体への使用は減りましたが、以下のような用途には今でも使われます。
-
木製ドア枠や手すりの塗装
-
シャッターや鉄柵などの細部
-
狭小地の短期塗装リフォーム
-
シリコンより安く済ませたいお客様向けプラン
※ただし、外壁メイン部分にはあまり使用されなくなってきています。
6. ウレタン塗料のまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 耐用年数 | 5〜8年 |
| 価格 | シリコンより安く、アクリルより少し高い |
| メリット | 柔軟性、密着性、コストのバランス |
| デメリット | 耐久性や防汚性にやや劣る |
7. ウレタン塗料はおすすめか?
✅ 向いている人:
-
初期費用を抑えたい
-
外壁以外(鉄部・木部)の塗装をしたい
-
定期的に塗り替える前提で使いたい
❌ 向いていない人:
-
10年以上塗り替えたくない
-
汚れやすい立地に住んでいる
-
耐久重視・高機能塗料を求める人
結論
ウレタン塗料は「コスパ重視」「補修中心」「複雑な部材対応」といったニーズに応えることができますが、外壁全体に長期的な塗膜性能を求めるなら、シリコン以上の塗料を選ぶのがおすすめです。
③シリコン塗料
シリコン塗料とは、主成分にシリコン系樹脂(有機シリコン)を使用した塗料で、現在の外壁塗装における主流塗料です。
「価格」と「耐久性」のバランスが良く、戸建住宅やアパートなど幅広い建物で使用されており、外壁・屋根ともに選ばれることの多い塗料です。
1. シリコン塗料の主な特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 耐久性に優れる | 耐用年数8~12年程度。ウレタンより長持ち。 |
| ✅ コストパフォーマンスが高い | 性能と価格のバランスが良く、一般住宅に最適。 |
| ✅ 汚れに強い | 親水性により雨で汚れを洗い流しやすい。 |
| ✅ ツヤ・発色が長持ち | 美しい見た目が長期間維持されやすい。 |
| ❌ 密着力はやや劣る | 細かい部材にはウレタン塗料の方が適することも。 |
| ❌ 塗膜が硬め | 柔軟性が低く、下地のひび割れには追従しにくい。 |
2. 耐久性と価格感
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約8〜12年(使用塗料によって差あり) |
| 塗料グレード | 中〜上級クラス |
| 平均価格帯 | 1㎡あたり2,200〜3,000円(材料+施工費) |
| 備考 | 日本ペイント「パーフェクトトップSi」やエスケー化研「クリーンマイルドシリコン」などが人気商品。 |
3. シリコン塗料の向いているケース
-
10年前後の塗り替えサイクルを希望している方
-
コストと耐久性のバランスを重視したい方
-
標準的な住宅外壁に適した塗料を探している方
-
長持ちする見た目を保ちたい方
4. 他の塗料との比較
| 種類 | 耐用年数 | 価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アクリル塗料 | 3〜5年 | ◎ 安価 | 短命・現在は非推奨 |
| ウレタン塗料 | 5〜8年 | ○ 手頃 | 柔軟性・密着性◎ |
| シリコン塗料 | 8〜12年 | △ 中価格 | 現在の主流。コスパ◎ |
| フッ素塗料 | 12〜15年 | ✕ 高価格 | 高耐久・撥水性に優れる |
| 無機塗料 | 15〜20年 | ✕✕ 非常に高価 | 半永久的耐久・超高性能 |
5. よく使われるメーカーと商品例
| メーカー | 商品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本ペイント | パーフェクトトップ | ラジカル制御型シリコン塗料。高耐久でコスパ◎ |
| エスケー化研 | クリーンマイルドシリコン | 低汚染性・防かび・防藻性能に優れる |
| 関西ペイント | セラMシリコンⅢ | 高光沢・高耐久のハイグレードタイプ |
6. 注意点
-
シリコンでもピンキリ:シリコン含有量や添加剤の差で、グレードが大きく変わる。
-
下地との相性:既存の塗膜や外壁素材により、下塗り材や施工方法を変える必要がある。
-
施工技術が重要:どんなに良い塗料でも、職人の技術が伴わないと効果が発揮されない。
7. シリコン塗料はおすすめか?
✅ おすすめな人:
-
初めて外壁塗装をする
-
10年周期でメンテナンスしていく予定
-
長く持って、でも高すぎない塗料を希望する
❌ 向かない人:
-
15年以上メンテ不要を目指す人(→フッ素・無機を検討)
-
雨風や紫外線が特に強いエリアに住む方(→高グレードシリコンまたはフッ素)
結論
シリコン塗料は、住宅の外壁塗装において最もバランスの取れた選択肢です。初めての塗り替えでも、リピートでも、多くの施工業者が推奨する「間違いない選択」と言えるでしょう。
④フッ素塗料
フッ素塗料とは、フッ素樹脂を主成分とする高耐久・高性能な外壁塗料です。東京スカイツリーや高速道路の橋梁など、極めて高い耐久性が求められる建造物にも採用されている塗料です。
一般住宅にも使用されるようになりつつありますが、他の塗料に比べて価格は高めです。
1. フッ素塗料の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 耐久性が非常に高い | 15年〜20年程度の耐用年数。塗り替え頻度が減らせる。 |
| ✅ 防汚・撥水性能に優れる | 汚れにくく、雨で自然に洗い流されやすい。 |
| ✅ 紫外線・熱に強い | 劣化・色あせが非常に少ない。 |
| ✅ 光沢感が長続き | ツヤのある美しい外観を長期間キープできる。 |
| ❌ 価格が高い | シリコン塗料の1.5〜2倍の価格帯。 |
| ❌ 硬くて割れやすい素材に不向き | 柔軟性が低いため、動きのある下地には追従しにくい。 |
2. 耐用年数と価格感
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約15〜20年 |
| 平均価格帯 | 1㎡あたり3,500〜4,800円(材料+施工費) |
| コストパフォーマンス | 高い初期費用だが、長期的には経済的になるケースも |
3. フッ素塗料が向いているケース
-
長期間塗り替えたくない人
-
紫外線や塩害の影響を受けやすい地域(例:海沿い、日当たりの強い立地)
-
美観を長く保ちたい人(艶・色あせが少ない)
-
高層住宅、店舗など頻繁に足場を組めない建物
4. 他の塗料との比較
| 塗料 | 耐用年数 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| アクリル | 3〜5年 | 安価・短命・汚れやすい | ◎ 非常に安い |
| ウレタン | 5〜8年 | 柔軟性あり・コスパ中程度 | ○ 安め |
| シリコン | 8〜12年 | 主流塗料・バランス◎ | △ 中価格 |
| フッ素 | 15〜20年 | 超高耐久・高性能 | ✕ 高価格 |
| 無機 | 15〜25年 | フッ素以上の超高耐久 | ✕✕ 非常に高価 |
5. 主なメーカーと代表製品
| メーカー | 商品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本ペイント | ファイン4Fセラミック | 4フッ化フッ素樹脂使用、高耐久・低汚染性 |
| エスケー化研 | クリーンマイルドフッソ | 高耐候・耐薬品性に優れた住宅用フッ素塗料 |
| 関西ペイント | アレスアクアフッソ | 水性で環境配慮型、艶あり・なしが選べる |
6. 注意点・施工時のポイント
-
塗料価格が高いため、業者によって見積もり差が出やすい
-
塗膜が硬めなので、下地の動きがある場所は別塗料を検討
-
艶消しタイプが少ないため、仕上がりの質感に注意
7. フッ素塗料はおすすめか?
✅ おすすめな人:
-
外壁を長期間メンテナンスフリーにしたい
-
美しいツヤを長持ちさせたい
-
外壁にコケ・カビ・色あせを防ぎたい
-
塗装コストを“長期的視点”で抑えたい
❌ 向かない人:
-
初期費用をとにかく安く済ませたい人
-
短期間で色変更・塗り替えを考えている人
結論
フッ素塗料は「長持ち・キレイ・汚れにくい」という三拍子が揃った高性能塗料です。初期費用は高いものの、長期的には再塗装の回数を抑えられるため、トータルコストを抑えたい方には非常におすすめです。
⑤ 無機塗料
無機塗料とは、ガラスや石などの無機物を主成分に配合した塗料のことです。無機成分は紫外線や熱、雨風に強く、極めて高い耐久性・防汚性・不燃性を持っています。
有機塗料(アクリル・ウレタン・シリコン・フッ素など)とは異なり、「劣化しにくい性質」が最大の特徴です。
1. 無機塗料の主な特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 超高耐久性 | 耐用年数は15〜25年。最長クラスの性能。 |
| ✅ 防汚・防カビ性に優れる | 雨で自然に汚れが流れ落ちるセルフクリーニング性能。 |
| ✅ 紫外線に非常に強い | 紫外線での塗膜劣化が極めて少ない。 |
| ✅ 不燃性あり | 火に強く、燃えにくい特性を持つ。 |
| ❌ 価格が非常に高い | シリコン塗料の2〜3倍程度。 |
| ❌ 塗膜が硬いため割れやすいケースも | 柔軟性の必要な下地には注意が必要。 |
2. 耐用年数・コスト
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約15〜25年 |
| 平均価格 | 1㎡あたり4,000〜6,000円(材料+施工費) |
| ランニングコスト | 初期費用は高いが、長期的には再塗装回数を減らせて経済的 |
3. 他の塗料との比較
| 種類 | 耐用年数 | 価格感 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アクリル塗料 | 3〜5年 | ◎ 非常に安い | 劣化が早く、現在は非推奨 |
| ウレタン塗料 | 5〜8年 | ○ 安め | 柔軟性・密着力が高い |
| シリコン塗料 | 8〜12年 | △ 中価格 | 現在の住宅塗装の主流 |
| フッ素塗料 | 15〜20年 | ✕ 高価格 | 高耐久・防汚性も高い |
| 無機塗料 | 15〜25年 | ✕✕ 非常に高価 | 最高クラスの性能と耐久性 |
4. 主な無機塗料のメーカーと代表製品
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本ペイント | アプラウドシェラスターNEO | 無機とフッ素のハイブリッド塗料。超高耐久。 |
| エスケー化研 | プレミアム無機 | 高耐久・高親水性でセルフクリーニング性能あり。 |
| 関西ペイント | アレスダイナミックMUKI | ガラス系無機で光沢長持ち。高密着性能も強み。 |
5. 無機塗料の向いているケース
-
将来的に外壁の塗り替え回数を減らしたい方
-
高層住宅や公共施設など、足場設置コストが高い建物
-
紫外線や雨風にさらされやすい立地の家(海沿い、山沿い等)
-
外壁の美しさを20年近くキープしたい方
-
不燃性能が必要なエリアや建物用途
6. 注意点
-
柔軟性がやや低いため、ひび割れしやすい外壁(モルタルなど)には適さないことがある。
-
施工には高い技術力が必要:誰が塗るかによって効果が大きく異なる。
-
見積の比較が必須:無機といいつつ「実はフッ素が主体」のハイブリッド製品も多い。成分構成を確認すること。
7. 無機塗料はおすすめか?
✅ おすすめな人
-
20年近く塗り替えたくない人
-
美観と機能性の両立を求める人
-
初期投資が可能な方
-
外壁が比較的動きにくい(サイディング等)
❌ おすすめしづらい人
-
予算が限られている
-
木部や鉄部の塗装を中心にしたい
-
柔軟性の高い塗膜が必要な箇所が多い
結論
無機塗料は「超長寿命」かつ「防汚・不燃・高美観」を誇る最高クラスの外壁塗料です。初期費用は高めですが、1回の塗装で20年近く持たせたい方にとっては、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢になります。
無機塗料の採用を検討している方は、「製品の成分構成」や「施工業者の技術力」をしっかり確認したうえで判断すると良いでしょう。
⑥ウレア塗料
ウレア塗料(ポリウレア塗料)とは、近年注目されている高性能な防水・防食塗料の一種で、ポリウレア樹脂を主成分とした塗料です。建築・土木・工業・防水などさまざまな分野で使われています。
特徴
1. 非常に高い耐久性
-
摩耗、衝撃、化学薬品、紫外線、塩害に強く、非常に過酷な環境下でも性能を維持します。
-
通常のウレタンやエポキシよりも優れた耐候性・耐薬品性を持ちます。
2. 超速硬化性
-
吹き付け後、数秒〜数分で硬化し、短時間で作業完了が可能。
-
工場の床、防水工事などで「即日復旧」が求められる現場に最適。
3. 伸縮性・柔軟性が高い
-
コンクリートのクラック追従性能があり、下地の動きに対応可能。
-
屋上や橋梁など、構造物の動きが大きい場所に適しています。
4. 厚膜施工が可能
-
一度の吹き付けで1mm以上の厚膜形成ができる(一般塗料は100μm前後)。
-
重防食、防水層としての使用に最適。
成分と構造
ポリウレアは、イソシアネート化合物とポリアミン化合物を高反応で組み合わせて硬化する塗膜です。ポリウレタンのようにポリオールではなく、ポリアミンと反応する点が大きな違いです。
🏗️ 主な用途
| 用途 | 具体例 |
|---|---|
| 防水工事 | 屋上、駐車場、地下ピット、防水層 |
| 防食工事 | 工場床、薬品槽、下水処理施設 |
| 建築・土木 | 橋梁、トンネル、護岸構造物 |
| 車両・設備 | トラック荷台、車両下部、戦車、パイプ保護 |
注意点
-
高価:通常のウレタンやシリコン塗料に比べ、材料費・施工費ともに高い。
-
専用の機器が必要:高圧温調タイプの二液同時スプレー装置での施工が必要。
-
専門知識と技術が必要:温度管理・混合比管理が難しく、未熟な施工者では不具合が生じる。
まとめ
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★(非常に高い) |
| 施工性 | ★★★☆☆(機械と経験が必要) |
| コスト | ★★☆☆☆(高価) |
| 用途の広さ | ★★★★★ |
⑦有機HRC塗料
有機HRC塗料は、主に重防食用途(橋梁・プラント・タンク・港湾構造物など)で使用される高機能塗料で、「高耐久・高機能な有機系重防食塗料」として開発された製品群です。以下に詳しく解説します。
有機HRC塗料とは?
「HRC」は通常、製品やメーカーによって意味が異なる場合がありますが、重防食分野では以下のような意味合いで使われています:
-
HRC = High Rust-protection Coating(高防錆塗料)
-
または、メーカーによっては「Hybrid Resin Coating(ハイブリッド樹脂塗料)」の略として使われることもあります。
つまり「有機HRC塗料」とは、有機樹脂をベースとした高耐久性・高防錆性の塗料のことです。
主な特徴
1. 高い防錆性(重防食)
-
鉄鋼構造物に対して非常に高い防錆性能を発揮。
-
塩害や高湿度環境でも長期間腐食を防ぐ。
2. 高耐候性・長寿命
-
紫外線や熱、風雨などに強く、15年~20年超の長寿命設計も可能。
-
メンテナンス周期が長く、LCC(ライフサイクルコスト)削減に寄与。
3. 有機無機ハイブリッド技術
-
無機成分(シリカなど)を配合することで、緻密で強靭な塗膜を形成。
-
ひび割れ・クラックにも強い。
4. 環境対応型も多数
-
VOC低減や水性化技術も進んでおり、環境負荷を抑えた製品も登場。
主な用途
| 適用対象 | 内容 |
|---|---|
| 橋梁 | 鋼橋の重防食塗装(国交省の防食仕様に適合) |
| 港湾・沿岸部構造物 | 潮風や塩害対策が必要な鉄部 |
| プラント・煙突 | 高温・高湿・腐食性ガス環境下 |
| 鉄塔・鉄骨構造物 | 高所・屋外の長期塗装が必要な箇所 |
構成例(一般的な有機HRC塗装仕様)
| 工程 | 使用塗料 | 塗膜厚 |
|---|---|---|
| 1次 | 有機ジンクリッチプライマー | 75μm |
| 2次 | エポキシ中塗り(高固形分) | 125μm |
| 3次 | 有機HRC上塗り(耐候型) | 50μm |
| 合計 | ― | 250μm以上(重防食仕様) |
注意点
-
専門の仕様書や防食基準に基づく選定が必要(例:JIS K 5516、国交省の鋼道路橋防食便覧 など)
-
一般住宅には使われることはほぼなく、産業・土木インフラ向けの用途が中心です。
-
製品ごとに「HRC」の意味や性能が異なるため、各メーカーの技術資料を確認するのが確実です。
有機HRC塗料を扱う主なメーカー(例)
| メーカー | 製品名例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 関西ペイント | アレスHRC、スーパーコートHRCなど | 橋梁やタンク向けの高防食塗料 |
| 日本ペイント | クリンカラーHRCシリーズなど | エポキシとウレタンをベースにした長寿命設計 |
| エスケー化研 | SKハイプロンHRCなど | 高機能重防食+環境対応型 |
まとめ
-
有機HRC塗料とは、有機系高耐久重防食塗料のこと
-
高防錆・高耐候・長寿命で、橋梁・プラント・沿岸構造物などの重防食用途に用いられる
-
製品によって「HRC」の定義や機能が異なるため、使用前に必ず製品仕様書の確認が必要
⑧光触媒塗料
光触媒塗料(ひかりしょくばいとりょう)とは、太陽光(主に紫外線)に反応して汚れを分解・除去する機能を持つ塗料のことです。防汚性能や空気浄化作用を備えた、高機能外壁塗料として注目されています。
光触媒とは?
▶ 原理(基本メカニズム)
光触媒塗料の主成分は、酸化チタン(TiO₂)という物質です。これが紫外線に当たることで下記の働きをします:
-
分解力(セルフクリーニング)
-
紫外線を受けると強力な酸化力(ラジカル)が発生
-
有機物(排ガス・油・カビ・菌などの汚れ)を分解
-
-
親水性
-
表面が水と馴染みやすくなり、雨水で汚れを洗い流す
-
油汚れや排気ガスも付着しにくい
-
光触媒塗料の特徴とメリット
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 🍃 セルフクリーニング効果 | 雨水で自動的に外壁の汚れが落ちるため、美観を長期間保持できる |
| 🌬 空気清浄機能 | NOx(窒素酸化物)やVOC(揮発性有機化合物)を分解し、大気浄化にも貢献 |
| 🔥 防カビ・防藻効果 | カビや藻の原因菌も分解されやすく、衛生的 |
| 💡 長寿命 | 塗膜そのものの耐久性も高く、15年〜20年以上持つ製品も |
デメリット・注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ☁ 日陰では効果が弱い | 紫外線が当たらない面(北面・高架下など)では分解効果が十分に得られない |
| 💰 価格が高い | 一般塗料と比較して材料費・施工費が高め(㎡単価で数千円UPも) |
| 🧽 付着した無機汚れには非対応 | 砂・土・鉄粉など、分解できない汚れには効果が薄い |
| 🎨 選べる色が限られることも | 酸化チタンが白いため、暗色系のカラーでは効果が低下する場合がある |
光触媒塗料の主な用途
| 用途 | 詳細 |
|---|---|
| 戸建て住宅 | 外壁・屋根・塀などの美観維持、防汚効果 |
| マンション・ビル | 外壁や外装材の長寿命化・メンテナンスコスト削減 |
| 公共施設 | 環境配慮・大気浄化性能への期待(学校・役所など) |
代表的な製品(例)
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本特殊塗料 | 光触媒コート ECO-EX | セルフクリーニング+抗菌防カビ |
| オプティマス | ダークサーモ光触媒 | 遮熱+防汚のハイブリッド機能 |
| TOTO | ハイドロテクトカラーコート | 外壁タイル向け、空気浄化機能で有名 |
| フッ素系との組合せ | 光触媒フッ素塗料 | フッ素の耐久性+光触媒の自己洗浄効果 |
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寿命 | 15〜20年と非常に長持ち |
| コスト | 中〜高価格帯(シリコンより高く、フッ素に近い) |
| メリット | 汚れに強く、美観を長く維持可能。空気もキレイに |
| デメリット | 紫外線が届かない面では効果が薄く、コストもやや高め |
こんな方におすすめ
-
美観を長く保ちたいお施主様
-
高所外壁で足場メンテナンスを頻繁にしたくない方
-
環境意識の高い公共施設・商業施設の管理者
⑨遮熱塗料
遮熱塗料(しゃねつとりょう)とは、太陽光に含まれる近赤外線(IR:Infrared)を反射することによって、屋根や外壁の表面温度上昇を抑え、室内温度の上昇を軽減する塗料のことです。特に夏季の冷房負荷を減らす目的で多く使われています。
遮熱塗料の仕組み
遮熱塗料は、赤外線を反射する特殊な顔料(遮熱顔料)を含んでいます。
太陽光のエネルギー構成:
-
紫外線(UV):約3%
-
可視光線(目に見える光):約45%
-
赤外線(IR):約52% ← これが熱の原因!
遮熱塗料はこの「赤外線(近赤外線)」を主に反射し、屋根や外壁の温度上昇を抑えます。
遮熱塗料のメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表面温度の抑制 | 屋根で最大20〜30℃程度、外壁でも10〜15℃の温度差が生じることも |
| 室内温度も低下 | 2〜4℃程度下がる例もあり、特に2階や最上階で効果が体感されやすい |
| 冷房費削減 | 空調負荷が減り、省エネ・節電につながる(最大10〜15%削減例も) |
| 建材の劣化抑制 | 高温による熱膨張や素材劣化の抑制に寄与 |
| 環境配慮 | 都市のヒートアイランド現象対策にも効果あり |
デメリット・注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 濃色は遮熱効果が弱い | 白や淡色の方が遮熱効果は高く、黒や濃い色は効果が下がる |
| 断熱とは違う | 遮熱は熱を反射するだけで、保温性や断熱性はない(冬は効果なし) |
| 効果が落ちる場合も | 汚れがつくと反射率が下がり、性能が低下する可能性がある |
| 価格がやや高め | シリコン塗料よりやや高く、一般的にはフッ素塗料と同程度 |
遮熱塗料の主な使用箇所
| 部位 | 効果が出やすい理由 |
|---|---|
| 屋根(特に金属屋根) | 日射を最も受ける場所で、温度差が大きく出る |
| 外壁(南面・西面) | 夏季に直射日光が当たる部分に特に効果的 |
| 工場・倉庫・体育館 | 大型建物で空調コストが高い場合に有効 |
代表的な遮熱塗料製品(国内)
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 関西ペイント | アレスクールシリーズ | 高い反射率とカラーバリエーションが豊富 |
| エスケー化研 | クールタイトシリーズ | コストパフォーマンスが高く戸建て向けに人気 |
| 日本ペイント | サーモアイシリーズ | 下塗りにも遮熱性能があり効果が高い |
| 水谷ペイント | 快適サーモシリーズ | セメント瓦・スレート・金属屋根に対応可 |
| 菊水化学工業 | キクスイ遮熱シリーズ | 外壁用にも強い遮熱効果を発揮 |
遮熱効果の数値イメージ(例)
| 条件 | 一般塗料 | 遮熱塗料 |
|---|---|---|
| 屋根表面温度 | 約65℃ | 約40℃(−25℃) |
| 室内温度(最上階) | 約32℃ | 約29℃(−3℃) |
| 電気代 | 年間¥100,000 | 年間¥90,000(−10%) |
※ 建物構造・立地・日射条件により異なります
遮熱 vs 断熱の違い
| 分類 | 遮熱塗料 | 断熱塗料 |
|---|---|---|
| 主な作用 | 赤外線を反射して熱を入れない | 熱を蓄えて通さない(保温) |
| 季節 | 主に夏向き | 夏も冬も対応可能 |
| 価格帯 | 中〜高 | 高め(遮熱より高い傾向) |
| 重ね塗り | 薄膜でOK | 厚膜が必要で乾燥時間も長い |
まとめ
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 断熱性 | ❌(なし) |
| 遮熱性 | ◎(高い) |
| 寿命 | ○(シリコンで10〜15年程度) |
| 費用対効果 | △〜◎(建物の条件による) |
遮熱塗料がおすすめなケース
-
2階が非常に暑くて困っている住宅
-
工場や倉庫など空調コストを削減したい建物
-
南向き・西向きの壁面が直射日光を受けている物件
-
屋根に金属素材(ガルバ、折板、トタンなど)を使用している場合
⑩断熱塗料
断熱塗料(だんねつとりょう)とは、熱の移動(伝導・放射)を抑えることで、夏の遮熱+冬の保温という両方の効果を発揮する高機能塗料です。単なる「遮熱塗料」とは異なり、建物内の温度変化を緩やかにすることを目的とした塗料です。
断熱塗料の仕組み
断熱塗料には、塗膜内に中空セラミックビーズや断熱微粒子が含まれており、以下の3つの熱伝導を抑制します:
-
伝導熱の抑制:空気層を含む構造で熱が伝わりにくい
-
対流熱の遮断:熱の移動が起きにくくなる
-
輻射熱(赤外線)の反射:遮熱顔料と組み合わせて太陽熱も反射
つまり、夏は外からの熱を遮断し、冬は内側の熱が逃げにくくなるのが特徴です。
断熱塗料のメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 夏涼しく、冬暖かい | 遮熱+保温のダブル効果。冷暖房効率アップ |
| 光熱費の削減 | 電気代やガス代の節約に貢献(10~20%削減例も) |
| 遮音効果 | セラミック粒子構造が音も吸収しやすい |
| 耐久性が高い | 高機能製品は15〜20年の耐候性あり |
| 環境にやさしい | CO₂排出削減・SDGs対策にも有効 |
断熱塗料のデメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格が高め | シリコン塗料の1.5〜2倍程度(㎡単価で+1,000〜2,000円) |
| 色の自由度が少なめ | 遮熱性を持たせる関係で明るめの色が多い |
| 施工厚みが必要 | 通常塗料より厚膜仕上げが求められ、乾燥にも時間がかかる |
| 通気性の確保が重要 | 塗膜が厚くなりやすいため、通気設計が悪いと結露のリスクも |
使用箇所・おすすめ建物
| 使用部位 | 理由・効果 |
|---|---|
| 屋根(特に折板・ガルバリウム) | 夏の熱遮断、冬の保温効果が大きい |
| 外壁(南・西面) | 太陽光が長時間当たる箇所に有効 |
| 工場・倉庫 | 室内空調コストを大幅削減可能 |
| 学校・病院など公共施設 | 光熱費削減と快適環境維持の両立に貢献 |
代表的な断熱塗料製品
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日進産業 | ガイナ(GAINA) | 宇宙技術応用。断熱+遮熱+遮音+防音+防露+空気清浄 |
| 水谷ペイント | 快適サーモBio | 断熱と遮熱の両立。防カビ抗菌も兼ねる |
| エスケー化研 | クールテクトF/Si | 遮熱強化型だが、断熱効果も持つハイブリッド |
| 菊水化学 | 水系ファインコート遮熱NEO | 遮熱+断熱+環境対応型の水性塗料 |
遮熱塗料との違い(比較表)
| 比較項目 | 遮熱塗料 | 断熱塗料 |
|---|---|---|
| 熱の反射 | ◎(赤外線を反射) | 〇(やや反射) |
| 熱の伝導遮断 | ✕ | ◎ |
| 夏の効果 | ◎ | ◎ |
| 冬の効果 | ✕ | ◎(保温) |
| 価格 | 中程度 | 高め |
| 厚み | 薄膜(100〜200μm) | 厚膜(400μm〜1mm以上) |
| 機能性 | 単機能 | 多機能(防音・防露など) |
断熱塗料の費用相場(目安)
| 塗装部位 | 一般塗料 | 断熱塗料 |
|---|---|---|
| 屋根(30㎡) | 約10万円 | 約16万円〜 |
| 外壁(150㎡) | 約60万円 | 約90万円〜 |
| ※足場代・下地処理など別途 |
まとめ
-
断熱塗料 = 夏の遮熱+冬の保温を実現
-
省エネ+快適な住環境+長寿命塗膜がメリット
-
初期費用は高いが、光熱費削減+メンテ周期延長で長期的に経済的
-
遮熱塗料よりも高機能で万能型
⑪OEM塗料
OEM塗料とは、塗料業界において「OEM(Original Equipment Manufacturer)」の形で製造された塗料のことを指します。つまり、塗料メーカーが他社ブランド名で製造・供給する塗料のことです。
構造のイメージ
たとえば:
-
実際の製造元:関西ペイント
-
販売名:○○建装オリジナル塗料「スーパー耐久コート」
→ 実際は「アレスダイナミックTOP」と同等だった、というようなケースもあります。
OEM塗料の目的・メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 差別化 | 自社専用のブランド塗料として競合との差別化が可能 |
| 信頼性の担保 | 大手塗料メーカーが製造しているため、品質的には安心 |
| ブランド力強化 | 「○○工務店オリジナル塗料」として、企業ブランド向上に貢献 |
| 高利益率確保 | 自社商品として販売できるため、価格コントロールがしやすい |
OEM塗料の注意点・デメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 中身が不透明な場合がある | 一般ユーザーには「何の塗料がベースかわからない」ことも |
| 情報がネットで調べにくい | 製品名で検索してもデータシートや施工実績が出てこない |
| 後継品・改良品の情報が届きにくい | ベースとなる塗料が廃盤になっても気づかないこともある |
OEM塗料の実例(業界でよくあるケース)
| OEM塗料名(例) | 製造元(実態) | 備考 |
|---|---|---|
| ○○ホーム遮熱プロ | 日本ペイント | 「サーモアイ」のOEM版 |
| △△リフォーム無機トップ | SK化研 | 「プレミアム無機」と同等クラス |
| XYZ超耐候コート | 関西ペイント | 「アレスダイナミックTOP」OEM版 |
※製品名は仮名ですが、実際にこういったOEM例は多数存在します。
見積書で「OEM塗料」と書かれていたら?
見積書や提案書に「当社オリジナル塗料(OEM)」などと書かれていた場合、以下の点を確認すると良いでしょう:
質問リスト:
-
製造元はどの塗料メーカーですか?
-
元になっている市販塗料の名前はありますか?
-
製品のカタログ・仕様書・期待耐用年数を見せてください
-
JIS規格やF☆☆☆☆などの取得状況は?
OEM塗料のまとめ
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 品質 | 製造元がしっかりしていれば安心 |
| 透明性 | 低い場合がある(中身がわかりにくい) |
| 価格 | 高めに設定されるケースが多い |
| 信頼性 | 情報開示の姿勢次第で変わる |
おすすめの対応方法
-
お客様に対しては「OEMだから悪いわけではなく、製造元の明示と性能開示が大事」と説明すると信頼されます。
-
自社でOEM展開を考える場合も、「差別化+ブランド戦略+品質証明」をセットで進めると効果的です。
⑫ラジカル制御型塗料
ラジカル制御型塗料(ラジカルせいぎょがたとりょう)とは、外壁塗装における高耐候性塗料の一種で、「塗膜劣化の原因」である“ラジカル”の発生や拡散を抑える機能を持つ塗料です。近年、コストと性能のバランスに優れた次世代塗料として人気が高まっています。
⑬クリヤー塗料
クリヤー塗料とは、顔料を含まない透明な塗料のことで、外壁や素材の意匠(デザイン)や模様、質感をそのまま活かしつつ、保護機能を与える塗料です。
サイディングやコンクリート打ち放し、木部などの「素材感を見せたい外装材」に用いられることが多いです。
クリヤー塗料の定義と役割
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 透明性 | 塗膜に色がつかないため、既存の外壁デザイン(レンガ調・石目調など)をそのまま見せることが可能 |
| 保護機能 | 紫外線・風雨・汚れ・劣化から既存の模様や素材を守る |
| 艶出し・艶消し | 艶あり・3分艶・艶なしなど、仕上げ感をコントロールできる |
| 色褪せ対策には不向き | 元の外壁が既に劣化・変色していると、それを隠せない(※化粧効果はなし) |
メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| デザイン保持 | 特に「意匠性サイディング」の美しさを残したまま保護できる |
| 素材を活かした塗装 | 打ち放しコンクリートや木材などの意匠材との相性が良い |
| 汚れにくい | フッ素や無機タイプなら高い親水性や防汚性能を持つ |
| 将来の塗替えが柔軟 | 次回塗装時に色付き塗料に変更可能 |
デメリット・注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 劣化面には不向き | 外壁にチョーキングや色褪せ、シーリングのひび割れがあると塗装できない(劣化を隠せないため) |
| 下地の状態が重要 | 汚れ・カビ・クラック・白化などは事前にしっかり補修・洗浄が必要 |
| 透明なのでムラが目立つ | 塗装不良や吹き残し、艶ムラが目立ちやすい(高い施工技術が必要) |
| やや高価 | 耐候性を高めるにはフッ素や無機タイプを選ぶことになり、コストが上がる |
適用される外壁素材
| 素材・仕上げ | クリヤー塗装の適性 |
|---|---|
| 窯業系サイディング(模様入り) | ◎(模様や質感を保護) |
| 打ち放しコンクリート | ◎(コンクリートの質感維持) |
| 金属サイディング(柄入り) | ○(状態次第で施工可) |
| モルタル(単色・劣化あり) | ✕(通常は色付き塗料を使用) |
主なクリヤー塗料の種類と性能
| 種類 | 特徴 | 耐久年数の目安 |
|---|---|---|
| アクリルクリヤー | 安価だが耐久性は低い | 4〜6年 |
| シリコンクリヤー | コストと性能のバランス◎ | 8〜10年 |
| フッ素クリヤー | 高耐候・高耐久。紫外線に強い | 12〜15年 |
| 無機クリヤー | 最高クラスの耐候性・防汚性能 | 15〜20年 |
主な製品(例)
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本ペイント | ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 2液弱溶剤型。シリコン/フッ素から選択可 |
| 関西ペイント | アレスアクアシリカクリヤー | 水性クリヤー塗料。耐汚染性が高い |
| エスケー化研 | プレミアムUVクリヤーSi/F | 高耐候性・高密着。艶選択可 |
| 菊水化学 | KPクリヤーシリーズ | 窯業系サイディング向けのフッ素系クリヤーあり |
クリヤー塗料が向いているケース
✅ 築7〜10年以内で、外壁の模様が劣化していない家
✅ 意匠性サイディングや打ち放しコンクリートなどの見た目を重視したい家
✅ 色を変えたくない、今の風合いをそのまま維持したい方
クリヤー塗料が不向きなケース
-
すでに外壁がチョーキング・色褪せ・ひび割れしている
-
シーリングが破断・変色している(打ち直し後、目地が目立ってしまう)
-
塗装によって色替えやイメージチェンジを希望している
まとめ
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 見た目維持 | ◎(模様・質感そのまま) |
| 耐久性 | ○〜◎(塗料のグレード次第) |
| 色替え | ✕(できない) |
| 費用 | やや高め(耐久性を求めると) |
| 下地の要求レベル | 高い(劣化していないことが条件) |
⑭セメント撥水材
セメント撥水材とは、コンクリートやモルタルなどのセメント系素材に対して、表面からの水の侵入を防ぐために使用する防水・保護材です。塗料ではなく、水を弾く=撥水効果を持たせる専用の液体処理剤で、外壁・基礎・擁壁・打ち放しコンクリートなどの耐久性向上に使用されます。
🧪 セメント撥水材とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主成分 | シラン、シロキサン、フッ素樹脂など(単体または混合) |
| 対象素材 | コンクリート、モルタル、セメント系建材(押出成形板、ALC など) |
| 効果 | 水・雨・湿気の侵入を防止しつつ、通気性(透湿性)を確保する |
| 使用方法 | 刷毛・ローラー・スプレーで塗布し、素材に浸透させる |
セメント撥水材のメリット
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 水の侵入を防止 | 雨水・毛細管水・湿気などから躯体を守る |
| 素材の見た目を変えない | 無色透明のものが多く、打ち放しコンクリートやモルタルの意匠をそのまま活かせる |
| 通気性あり(透湿性) | 水蒸気は通すため、内部の結露や膨れのリスクを軽減 |
| 中性化・劣化の抑制 | 炭酸ガスや酸性雨などの侵入も抑制し、コンクリートの中性化・鉄筋腐食を防ぐ |
| 汚れ・カビ・エフロ防止 | 雨だれや白華(エフロ)現象を抑え、美観維持に貢献 |
注意点・デメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効果は永久ではない | 製品により5〜10年程度の再処理が必要な場合が多い |
| 表面劣化があると効果減少 | クラック・塩害・風化部位には別途補修が必要(下地が健全であることが前提) |
| 色付きはできない | 撥水材はあくまで“透明仕上げ”。色を変えたい場合は塗料が必要 |
| 防水ではない | 「撥水=水を弾く」だけで、完全な防水材とは別物です |
セメント撥水材の主な種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| シラン系 | 粒子が小さく深く浸透、素材を変色させにくい。主に打ち放しコンクリート向け |
| シロキサン系 | 表面に皮膜を形成、比較的浅い浸透。屋外モルタルやALC向けに使われる |
| フッ素系 | 高撥水性・防汚性に優れ、やや高価だが高耐久。 |
| 複合型(シラン+シロキサンなど) | 浸透性と表面保護のバランスが良い。最近の主流製品に多い構成 |
主な使用箇所・用途
| 用途 | 対象箇所 |
|---|---|
| 建物外壁 | コンクリート打ち放し・モルタル壁・化粧ブロックなど |
| 基礎・擁壁 | 雨水や地下水による劣化・白華現象防止 |
| 屋上パラペット | クラックからの水侵入を抑制 |
| 外構 | RC塀、花壇、階段まわりなど |
代表的なメーカーと製品(例)
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| ABC商会 | ハイドロテクトコート撥水剤 | 無機・有機複合タイプ。建築仕上材向け |
| 大日本塗料 | DNアクアガード | シラン系浸透性撥水剤。高い耐候性 |
| 菊水化学 | キクスイ撥水剤S | 外壁モルタル・化粧ブロックなどに適応 |
| エスケー化研 | SK浸透性撥水材 | ALCにも対応。打ち放しコンクリートの保護に最適 |
施工の注意点
-
施工前に高圧洗浄・乾燥が必要(浸透を妨げないため)
-
雨天・結露・含水率が高い場合は施工NG(撥水不良の原因)
-
*浸透型撥水材は塗りすぎないのが基本(ムラや白化の原因になる)
まとめ
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 耐久性 | ○(5〜10年目安) |
| 施工性 | ◎(刷毛・ローラー・スプレーでOK) |
| 意匠保持 | ◎(透明で美観を損ねない) |
| 防水性 | △(あくまで撥水、完全防水ではない) |
| 対象素材 | ◎(セメント・モルタル・ALC など) |
⑮防腐剤
防腐剤塗料(ぼうふざいとりょう)とは、木材や金属などの素材が腐食・腐朽・虫害を受けるのを防ぐために、腐敗防止機能を持たせた塗料のことです。特に木部(ウッドデッキ・外構フェンス・柱など)に使われるケースが多く、防腐・防虫・防カビ・防藻効果を同時に持つ製品が主流です。
防腐剤塗料とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 素材(主に木材)の腐食や菌・虫害による劣化を防ぐ |
| 成分 | 防腐剤(有機系 or 無機系)+ 顔料 or 樹脂(油性/水性) |
| 対象素材 | 木材(屋外木部が主)、一部金属やコンクリート用も存在 |
主な効果・機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 防腐 | 腐朽菌や湿気による木材の腐食を抑える |
| 防虫 | シロアリ・キクイムシ・甲虫などの食害防止 |
| 防カビ・防藻 | 黒カビ・緑藻などの発生抑制 |
| 撥水・耐水性 | 水の浸透を防ぎ、木材の膨張・割れ・反りを防ぐ |
| 着色保護 | 着色機能を併せ持つタイプもあり、紫外線劣化を防ぐ |
木部用 防腐剤塗料の分類
| 分類 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|
| 浸透型(ステイン) | 木に浸透し内部から保護。木目を活かす | ウッドデッキ、ログハウス |
| 造膜型(ペンキ) | 表面に塗膜を形成して防水・防虫 | 屋外木部全般、色を変えたいときに有効 |
| 天然系(植物油ベース) | 自然素材で環境負荷が少ない。安全性重視 | DIY、無垢材など |
金属用の防腐剤塗料(防錆塗料との違い)
金属の場合、「防腐」=錆(腐食)を防ぐという意味で、防腐剤塗料 ≒ 防錆塗料と同義で使われることもあります。
| 金属用の防腐機能 | 代表製品 |
|---|---|
| サビ止めプライマー | エポキシ系防錆プライマー(JIS規格品)など |
| 重防食塗料 | ジンクリッチペイント・有機ジンクプライマー |
代表的な防腐剤塗料メーカーと製品
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 和信化学工業 | ガードラックシリーズ | 木部用・屋外屋内両対応・多彩な色展開 |
| キシラデコール(大阪ガスケミカル) | 標準タイプ/コンゾラン | プロ用木部塗料。抜群の浸透性と耐久性 |
| 日本エンバイロケミカルズ | ノンロットシリーズ | 人と環境に優しい防腐塗料。無垢材向け |
| 大谷塗料 | バトンシリーズ | 浸透型ステイン塗料。和風建築にも多用 |
| 日本ペイント | 木部用水性防腐ステイン | 水性で低臭・屋外木部向け |
塗布方法と注意点
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 表面処理 | サンダーやペーパーで旧塗膜・汚れを除去 |
| ② 下地乾燥 | 木材含水率15%以下が理想(湿っていると撥水不良) |
| ③ 塗布 | 刷毛・ローラー・スプレーで2回塗りが基本 |
| ④ 定期メンテ | 木部の種類や環境により2〜5年ごと再塗装推奨 |
防腐剤塗料の使用例
| 使用場所 | 使用目的 |
|---|---|
| ウッドデッキ | 紫外線・雨・シロアリ防止 |
| フェンス・門扉 | 美観+劣化防止 |
| 軒天・木製破風 | 雨の侵入やカビの防止 |
| 室内木材(※対応品のみ) | 防カビ・保護(無臭タイプを選定) |
まとめ
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 防腐性能 | ◎(適切な塗布で高耐久) |
| 防虫性能 | ◎(木部の大敵シロアリ対策に有効) |
| 美観保持 | ○(木目を活かす浸透型がおすすめ) |
| メンテナンス性 | △(再塗装は2〜5年が目安) |
| 安全性 | △〜◎(水性や自然系塗料を選べば高評価) |
⑯防錆剤
防錆剤(ぼうせいざい)とは、金属が空気中の酸素や水分、塩分などと反応して「サビ(酸化・腐食)」を起こすのを防ぐための薬剤・塗料・コーティング材のことです。鉄・鋼・アルミ・亜鉛・銅など、金属部材の長寿命化に不可欠な材料として、建築・土木・自動車・機械など幅広い分野で使用されています。
防錆剤の基本原理
金属が腐食する原因は主に以下の環境因子:
-
酸素(O₂)
-
水分(H₂O)
-
塩分(特にNaCl)
-
二酸化炭素(CO₂)
-
大気中の化学物質(SOx, NOx など)
防錆剤は、これらから金属表面を保護することで、酸化反応(サビ)を抑制します。
防錆剤の種類と分類
① 塗布型(塗料・コーティング)タイプ
| 種類 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|
| 防錆塗料 | 金属表面に塗膜を作り、外気と遮断。エポキシ系やウレタン系が主流 | 鉄骨・橋梁・機械など |
| さび止めプライマー(下塗り塗料) | 塗装の1層目に使う。防錆+上塗り密着力向上 | トタン屋根、鉄扉など |
| ジンクリッチペイント(亜鉛系) | 鉄より先に犠牲防食する亜鉛粉入り塗料 | 鉄塔、橋梁、配管など |
② 化学処理型(浸透・転換)タイプ
| 種類 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|
| 防錆油(防錆オイル) | 金属表面に油膜を形成。保管中の部品保護などに使用 | 自動車部品、金型、工具など |
| 防錆剤スプレー | 手軽に塗布可能。潤滑+防錆の製品も多い | バイク・門扉・農機具など |
| さび転換剤 | 既存の赤サビを黒サビ(安定酸化物)に変え、腐食を進行させない | 旧塗膜の補修現場など |
| 防錆水・防錆液 | 洗浄後に浸漬して防錆膜を形成 | 金属加工・機械部品の保管用 |
③ 気化性防錆剤(VCI:Volatile Corrosion Inhibitor)
| 特徴 | 使用方法 |
|---|---|
| 揮発成分が気体になって金属表面に吸着し、保護膜を作る | 包装紙・フィルム・袋・カートンに練り込んで金属製品を保護 |
| 接触しなくても効果を発揮するのが特長 | 電子部品・精密機器・輸出用資材などに使われる |
用途別・おすすめ防錆剤タイプ
| 用途 | おすすめ防錆剤 |
|---|---|
| 屋外鉄部(手すり・門扉・トタン) | エポキシ系さび止め塗料+ウレタン上塗り |
| 車・バイクの金属部 | 潤滑性のある防錆スプレー(CRC 5-56など) |
| 工場部品・金型の保管 | 防錆油 or 気化性防錆紙包装 |
| 配管・鋼橋・鉄骨 | ジンクリッチペイント(溶融亜鉛メッキ相当の防食力) |
| 海岸地域の鉄骨 | 重防食タイプ(JIS K 5621規格品など) |
主な製品例
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本ペイント | ハイポン20ファインプライマーⅡ | 2液型エポキシ防錆塗料。鉄・非鉄対応 |
| 関西ペイント | スーパーザウルスEX | 高密着型プライマー。シーラー兼用 |
| エスケー化研 | SKマイルドボーセイ | 鉄部用1液弱溶剤型防錆塗料 |
| シャーウィンウィリアムズ | ジンクリッチプライマー | 高亜鉛含有。橋梁・鉄骨向け |
| CRC(呉工業) | 5-56防錆スプレー | 潤滑+防錆+水置換機能でDIYにも便利 |
防錆処理の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 表面処理が最重要 | サビ・油分・旧塗膜を除去しないと密着不良や効果半減 |
| 塗布ムラ厳禁 | 膜厚不足=サビ再発リスク。重ね塗りや2回塗りが原則 |
| 天気・湿度管理 | 湿度85%以上や結露状態では施工NG(逆に錆を助長) |
| 定期的な点検と再処理 | 防錆塗料も劣化するため、5〜10年を目安に再塗装が必要 |
まとめ
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 主な目的 | 金属の腐食(酸化)を防ぐ |
| 対象素材 | 鉄、銅、アルミ、亜鉛合金など |
| 使用場面 | 塗装・部品保管・輸送・建築現場・DIY など幅広い |
| 処理方法 | 塗布・浸漬・気化性・スプレー など用途に応じて選定 |
| 注意点 | 表面処理・施工環境・定期メンテが肝心 |
⑰サビ転換剤
サビ転換剤(さびてんかんざい)とは、すでに発生している「赤サビ(酸化鉄(III))」を化学的に安定な「黒サビ(酸化鉄(II))」に変化(転換)させ、腐食の進行を抑える薬剤です。
ケレン(サビ落とし)を完全に行えない現場などで重宝される、下地処理用の防錆剤です。
サビ転換剤の仕組み
▶ 原理
赤サビ(Fe₂O₃)は不安定で水や酸素を呼び込むため腐食が進行します。
サビ転換剤はこの赤サビに反応し、安定な黒サビ(Fe₃O₄)や有機鉄錯体に変化させることで、腐食反応をストップさせるのです。
| 種類 | 状態 | 腐食のしやすさ |
|---|---|---|
| 赤サビ(Fe₂O₃) | 酸化鉄(III) | ❌ 非常に腐食が進む |
| 黒サビ(Fe₃O₄) | 酸化鉄(II,III) | ◎ 安定して腐食を抑える |
サビ転換剤のメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 重ケレンの省略が可能 | 完全にサビを落とさなくても使用できるため、省力化につながる |
| 防錆下地として使える | そのまま塗装できるタイプも多く、工程短縮に貢献 |
| 浸透力が高い | サビの奥まで成分が入り込み、転換処理が可能 |
| 火気不要・化学反応型 | 電気や熱を使わず、化学的にサビ処理ができる |
デメリット・注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 白サビ・黒皮・旧塗膜には効果なし | 赤サビ以外には基本的に反応しない |
| 下地によっては密着不良も | 塗料によっては転換被膜との相性に注意が必要 |
| 経年で再錆びる可能性あり | サビ転換剤自体には恒久的な防錆力はないため、上塗り必須 |
| 油・汚れ・水分はNG | 表面が汚れていると反応せず、性能が落ちる |
主な用途
| 使用場所 | 内容 |
|---|---|
| 鉄骨・鋼材 | 橋梁・建築現場などでのサビ補修 |
| トタン屋根・鉄板 | ケレンがしにくい場所の簡易サビ処理 |
| フェンス・門扉・手すり | DIYや部分補修に有効 |
| 自動車・バイク・農機具 | 赤サビ部へのスポット補修用途で人気 |
代表的な製品(国内)
| メーカー | 製品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 関西ペイント | ザビシャット | 赤サビ専用の転換剤。上塗り前の下地処理に使用 |
| アトムハウスペイント | サビ転換防錆剤 | ホームセンターでも入手可。刷毛塗りタイプ |
| エーゼット(AZ) | サビキラープロ | DIYでも人気。黒く変色してすぐ塗装可 |
| ニッペホームプロダクツ | サビキラーシリーズ | 水性タイプもあり、家庭用にも適応 |
| サビアウト | SABIOUT | 業務用向けの高反応性タイプ。鉄部修繕に使われる |
使用方法(基本手順)
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 表面処理 | ワイヤーブラシやサンドペーパーで浮きサビ・汚れを落とす(軽ケレン) |
| ② 清掃 | 油・水・ゴミを除去し、乾燥状態を確保 |
| ③ 塗布 | 刷毛またはローラーで、サビ部に均一に塗布(変色:赤→黒) |
| ④ 乾燥 | 数時間(製品により異なる)しっかり反応させる |
| ⑤ 上塗り | 転換後にサビ止め塗料や仕上げ塗装を行う |
まとめ
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 使用対象 | 主に赤サビの出た鉄部 |
| 施工難易度 | 低(DIYにも使える) |
| メリット | 重ケレン不要、工程短縮、コストダウン |
| 注意点 | 上塗り必須、白サビ・油・水分には効果なし |