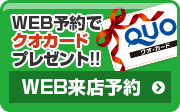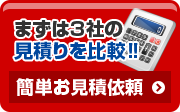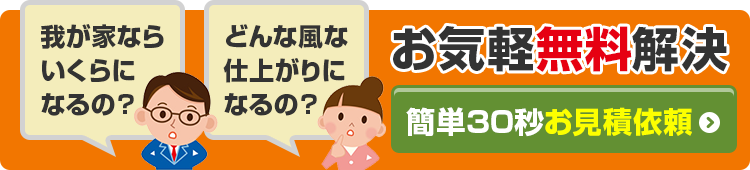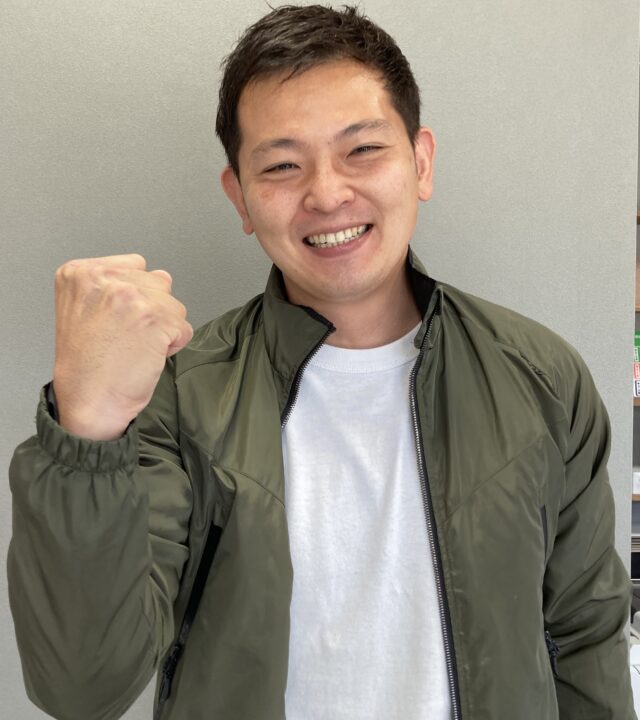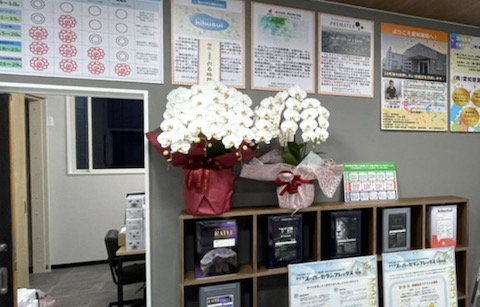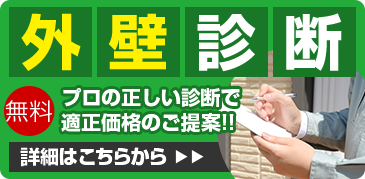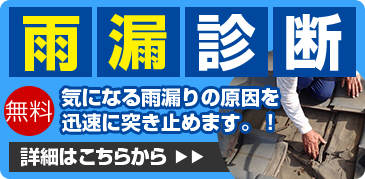用語集その④、作業編!!
2025.09.23 (Tue) 更新
①ケレン作業
ケレン作業(けれんさぎょう)とは、主に塗装工事や防水工事の前処理として行う「素地調整」の作業のことです。塗装やコーティングを施す前に、下地(鋼材、木材、コンクリート、旧塗膜など)のサビ・汚れ・旧塗膜・付着物などを除去して、塗料がしっかり密着できる状態にする目的で行われます。
目次
ケレン作業の主な目的
-
塗料の密着性向上
塗る面に汚れやサビがあると塗料がうまく定着せず、早期剥離や膨れの原因になります。 -
下地の劣化防止
サビやカビを放置したまま塗装すると、見えない部分で腐食が進行します。 -
仕上がりの品質向上
表面を平滑にすることで、均一できれいな塗膜を実現できます。
ケレン作業の種類(等級)
ケレンは目的や施工箇所に応じて「1種~4種」に分類されます。
| 等級 | 内容 | 具体的な作業内容 | 適用例 |
|---|---|---|---|
| 1種ケレン | ブラスト処理 | 高圧の砂や鋼粒を吹き付けて全面除去 | 発電所・橋梁など重防食が必要な鉄構造物 |
| 2種ケレン | 電動工具使用 | グラインダーやディスクサンダーでサビ・旧塗膜除去 | さびた鉄骨階段や鉄製手すりなど |
| 3種ケレン | 手工具併用 | ワイヤーブラシ、皮スキなど手作業中心 | 軽度のサビやチョーキング除去 |
| 4種ケレン | 清掃・洗浄中心 | 雑巾ふき、水洗いなど | 汚れのみの外壁、塗り替え前の軽い下地処理 |
使用される道具
-
ワイヤーブラシ
-
皮スキ
-
サンダー・グラインダー
-
高圧洗浄機
-
電動ディスクグラインダー
-
ケミカル(薬剤)によるサビ除去剤 など
注意点
-
ケレン不足は施工不良の原因
特に鉄部塗装では、ケレンを怠ると数ヶ月でサビが再発することもあります。 -
音や粉塵が出るため周囲への配慮が必要
集合住宅や近隣がある場所では作業時間や養生の工夫が求められます。
外壁塗装におけるケレンの例
-
雨戸やシャッターボックスの旧塗膜除去
-
ベランダ手すりや鉄骨階段のサビ落とし
-
木部の古いニスや汚れの除去
まとめ
ケレン作業は塗装工事の品質を左右する「最重要工程のひとつ」です。見えない部分の手間を惜しまないことで、塗膜の持ちや仕上がりが格段に向上します。信頼できる業者かどうかは、ケレン作業の丁寧さで分かるとも言えるでしょう。
②下地処理
外壁塗装における下地処理(したじしょり)とは、塗装を行う前に外壁の表面状態を整え、塗料がしっかり密着し、長持ちするようにするための重要な工程です。単なる「掃除」や「準備」ではなく、仕上がりの美しさ・耐久性・防水性に直結する非常に重要な作業です。
下地処理の目的
-
塗料の密着性を高める
-
外壁の劣化・傷みを補修する
-
美しく均一な仕上がりを実現する
-
塗装後の早期剥がれや不具合を防止する
外壁塗装における主な下地処理工程
| 工程名 | 内容 | 使用する工具・資材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高圧洗浄 | 汚れ・カビ・コケ・チョーキング粉などの除去 | 高圧洗浄機 | 必須工程。1日かかることも |
| ケレン作業 | サビや旧塗膜、付着物の除去 | ワイヤーブラシ、皮スキ、グラインダー等 | 特に鉄部や木部に重要 |
| クラック補修(ひび割れ補修) | 外壁のひび割れを埋める | コーキング材、樹脂モルタル等 | 幅や深さで補修方法が変わる |
| シーリング(コーキング)打ち替え | 目地部分の劣化したシーリング材の撤去・新設 | カッター、シーリングガン等 | 窯業系サイディングなどで重要 |
| パテ処理 | 小さな穴や段差を平らにする | パテ材、ヘラ等 | 美観向上目的。主に下地調整 |
| 素地調整剤・フィラーの塗布 | 下地の吸い込み止め・微細な凹凸の補修 | 微弾性フィラー、サーフェーサー等 | 塗装の下塗りとは別の意味合い |
| 養生 | 塗装しない箇所の保護 | マスキングテープ、ビニールシート等 | 窓や植栽、玄関などに実施 |
下地別の処理ポイント
-
モルタル外壁
→ クラック補修が重要。浮き・爆裂がある場合は左官補修。 -
サイディング外壁
→ シーリング(コーキング)の打ち替えが重要。反りや浮きのチェックも。 -
ALC外壁
→ 専用のシーリング材で目地補修。吸水性が高いためフィラー処理が必須。 -
鉄部・付帯部(雨戸・水切りなど)
→ ケレン・錆止め塗装が必須。
下地処理を省略するとどうなる?
-
数年で塗膜が剥がれる
-
水の浸入による構造材の腐食
-
膨れ・浮き・ムラの発生
-
美観の劣化が早まる
-
保証対象外になる可能性も
まとめ
下地処理は、塗装の仕上がりを左右する「縁の下の力持ち」です。表面がどれだけキレイに塗れていても、下地処理が不十分だと長持ちしません。特に外壁の状態が築10年以上経過している場合、下地処理の質=塗装の品質といっても過言ではありません。
③ローラー塗り
ローラー塗りとは、外壁塗装や屋根塗装などにおいて、塗料を「ローラー」と呼ばれる道具で塗布する施工方法です。塗装工事において最も一般的で、刷毛塗り(はけぬり)や吹き付け塗装と並ぶ代表的な塗装手段の一つです。
ローラー塗りとは?
ローラー塗りは、「筒状のスポンジ(ローラー)」に塗料を含ませて、壁や屋根の表面に転がすようにして塗装する方法です。ムラが出にくく、均一な仕上がりが得られやすいため、多くの塗装業者が採用しています。
ローラーの種類と使い分け
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| ウールローラー(万能タイプ) | 毛が長めで凹凸面にも対応 | モルタル、サイディングなど一般外壁 |
| 短毛ローラー | 平滑面向き。塗膜が薄めに仕上がる | 鉄部、室内、ドアなど |
| 中毛ローラー | 汎用性が高く、広く使われる | 外壁、屋根の下塗り〜中塗り |
| 多孔質ローラー(砂骨ローラー) | 塗膜を厚く付けられる特殊なローラー | 微弾性フィラーの下塗りに使用 |
| スモールローラー | 幅が狭く、細かい場所にも対応 | サッシ周りや細部の塗装に便利 |
ローラー塗りのメリット
-
飛散が少なく、近隣への配慮がしやすい
→ 吹き付け塗装に比べて、塗料が風で飛びにくい。 -
塗料のロスが少ない
→ 塗装面にしっかり密着させやすい。 -
仕上がりが安定して美しい
→ 均一な膜厚(塗膜の厚み)で塗りムラが出にくい。 -
狭い範囲や複雑な形状にも対応しやすい
ローラー塗りの注意点・デメリット
-
凹凸の深い面や細かい装飾には不向き
→ 刷毛や吹き付けとの併用が必要なことも。 -
手作業なので職人の技術差が出やすい
→ 適切な力加減、塗りスピード、塗布量が求められる。 -
施工時間が吹き付けより長くなる場合がある
外壁塗装でのローラー塗りの活用例
-
下塗り:フィラーやシーラーを均一に塗布
-
中塗り・上塗り:主剤塗料で耐候性や美観を確保
-
細部:スモールローラーや刷毛との併用で丁寧な仕上げ
まとめ
ローラー塗りは、高品質な仕上がりと周囲への安全性を両立できる非常に優れた塗装方法です。特に住宅地や商業地などでの塗装に適しており、外壁塗装では「標準的かつ信頼性の高い施工方法」として広く用いられています。
④刷毛塗り(はけぬり)
刷毛塗り(はけぬり)とは、塗装作業において「刷毛(はけ)」という道具を使って塗料を塗る、もっとも基本的で手作業による塗装方法のことです。ローラー塗りや吹き付け塗装と比べて、細かい作業や複雑な形状への対応力が非常に高いのが特徴です。
刷毛塗りとは?
「刷毛」とは、動物の毛や合成繊維などを束ねた塗装用の道具で、これに塗料を含ませて、塗る・伸ばす・なじませるといった繊細な作業を手作業で行う塗装技法です。主に細部・隅・入り組んだ箇所など、ローラーでは塗りにくい場所に使われます。
刷毛塗りのメリット
-
細かい部分に正確に塗れる
→ 窓枠まわり、配管の裏、入隅(角の内側)などに最適。 -
塗料の調整がしやすい
→ 濃度・量・伸びを職人の感覚で調整可能。 -
凹凸のある素材にも対応しやすい
→ 模様付きの外壁や木部などに向いている。 -
仕上がりが繊細で美しい
→ 熟練職人が丁寧に塗ることで、艶や質感が引き立つ。
刷毛塗りのデメリット・注意点
-
施工スピードが遅い
→ 広範囲をすべて刷毛で塗ると時間がかかる。 -
職人の技術差が出やすい
→ 塗りムラや刷毛跡が出ることもある。 -
塗布面積がローラーより小さいためコストが上がる場合も
よく使われる刷毛の種類
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 筋違(すじかい)刷毛 | 斜めにカットされた先端で、細部に塗りやすい | 隅や角、入隅などの細部 |
| 平刷毛 | 幅広くまっすぐな形状 | 広い平面、木部や戸袋など |
| 目地刷毛(ねじばけ) | 細長い形状で溝にフィット | サイディングの目地部分など |
| タッチアップ刷毛 | 修正用の小型刷毛 | 部分補修、塗り残し対応 |
外壁塗装における刷毛塗りの実際
-
ローラーでは届かない隙間や段差部分の補助塗装
-
鉄部(雨戸・手すり・配管など)の精密仕上げ
-
雨樋や軒天の塗り分け部分
-
塗装後のタッチアップ補修(塗り残し対応)
まとめ
刷毛塗りは、機械ではできない「人の手だからこそ可能な、細やかで丁寧な仕上げ」を実現するために欠かせない技法です。特に外壁塗装の仕上がりや耐久性を左右する細部の塗装では、刷毛塗りの巧拙が施工品質に直結します。
⑤吹き付け塗装
吹き付け塗装(ふきつけとそう)とは、専用のスプレーガン(コンプレッサーを使った噴霧機)を使って、塗料を霧状にして壁面に吹き付ける塗装方法です。ローラーや刷毛による塗装とは異なり、独特の質感・模様を出せるのが最大の特長で、意匠性が求められる住宅や店舗、マンションなどでも使用されます。
吹き付け塗装とは?
スプレーガンにより、塗料を細かい霧状にして噴射することで、外壁全体に均一かつスピーディに塗装ができる方法です。手作業のローラー塗装に比べて仕上がりに立体感や表情を出せることが特徴です。
吹き付け塗装のメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工スピードが速い | 広い面積を一気に塗れるため、大規模物件で有利 |
| 模様・質感が自由に出せる | 吹き付け専用塗材を使うことで、砂壁調・リシン・スタッコ・吹き戻し模様などを演出可能 |
| 塗膜が均一に仕上がる | 膜厚のばらつきが少なく、見た目が美しい |
| 凹凸面にも塗りやすい | サイディングや擬石調外壁などにも対応可能 |
吹き付け塗装のデメリット・注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 塗料の飛散が多い | 周囲の車や建物に塗料が飛ぶ可能性があり、養生が必須 |
| 風の影響を受けやすい | 屋外では風により塗料が流され、施工不可になる日もある |
| 施工には高い技術が必要 | 吹きムラ、垂れなどが起きやすく、職人の経験値が求められる |
| 材料の使用量が多くなる傾向 | 空気中への飛散が多いため、塗料のロスが発生しやすい |
| 近隣への配慮が必要 | 騒音や塗料の臭い、飛散リスクにより、住宅密集地では敬遠されることも |
吹き付け塗装で使われる模様仕上げ(仕上げの種類)
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| リシン吹き | 細かい砂粒を混ぜた塗料で、ザラザラとした質感になる |
| スタッコ吹き | 厚膜仕上げで、重厚感ある外観に。ツブツブした模様が特徴 |
| 吹き戻し仕上げ(タイル吹き) | 吹き付け後、表面を軽く平らにすることで、模様を押さえた落ち着いた仕上げに |
| ボンタイル吹き | 弾性塗料を使って模様を作り、弾力性・防水性を兼ね備えた仕上がりになる |
外壁塗装での活用例
-
大型の集合住宅や公共施設の外壁
-
デザイン性の高い住宅や店舗の外観演出
-
下地に凹凸やクラックが多いモルタル壁のリカバー
近年ではローラー塗りが主流になっている理由
-
飛散リスクが高く近隣トラブルになりやすいため
-
環境規制により溶剤系塗料の制限が厳しくなった
-
養生コストや施工管理の手間がかかる
-
ローラーでも十分に美しい仕上がりが得られるようになったため
まとめ
吹き付け塗装は、高意匠性・短時間施工・広範囲対応などの強みを持つ塗装技法です。ただし、施工環境(周囲との距離・風・養生)や職人の技術レベルによってはデメリットも大きくなるため、使用の可否は慎重に判断する必要があります。
⑥養生作業(ようじょうさぎょう)
養生作業(ようじょうさぎょう)とは、塗装しない部分を塗料の飛散・付着から保護するために、ビニールシートやマスキングテープなどを用いて覆う作業のことです。塗装前の準備工程の中でも非常に重要で、仕上がりの美しさや近隣への配慮、事故防止に直結するプロの技術が求められる作業です。
養生作業の目的
-
塗装しない箇所を保護するため
-
仕上がりの境界を美しく整えるため
-
塗料の飛散によるトラブルを防ぐため
-
作業効率を上げるため(養生により作業範囲が明確になる)
主な養生対象(塗装しない場所)
| 養生箇所 | 理由 |
|---|---|
| 窓ガラス・サッシ | 塗料の飛散や付着を防止 |
| 玄関ドア・ポスト・門扉 | 意匠性を保つため |
| ベランダの床や手すり | 滑りやすくなるのを防ぐ |
| 室外機・給湯器・電気メーター | 故障や安全性の確保 |
| 車・植物・外構部分 | 飛散による汚れ・損傷を防止 |
| 近隣の建物や壁 | トラブル防止とマナー対応 |
🛠 養生に使われる道具・材料
| 道具名 | 用途 |
|---|---|
| マスキングテープ | 細かな縁取りやライン出しに使用 |
| マスカー(テープ付きビニール) | 大面積の養生に便利。窓や壁面などに貼る |
| ブルーシート | 足場の下や庭などの養生に使用 |
| ノンスリップシート | 玄関や通路などの歩行面に使う滑り止め養生材 |
| 養生ネット(メッシュシート) | 足場全体を覆い、近隣への飛散防止に使用 |
養生作業のポイント
-
ラインが真っ直ぐ出ているか(仕上がりの美しさ)
-
テープの浮きや隙間がないか(塗料の漏れ防止)
-
空気の通り道や換気に配慮されているか
-
室外機や給湯器など熱を持つものに無理な養生をしていないか
-
住人が日常生活できるように考慮されているか(ドア開閉・窓の一部開放など)
養生の撤去とその後
塗装完了後、養生は丁寧に剥がされます。
この際、塗膜がまだ完全に乾いていないと塗料の剥がれやヨレが生じるリスクがあるため、タイミングと手順に細心の注意が必要です。また、剥がしたあとの微調整や清掃作業も仕上げの一環として行われます。
養生を怠るとどうなる?
-
塗料がサッシやガラスに付着し、取れなくなる
-
周囲に塗料が飛び、近隣トラブルになる
-
塗り分けラインがガタガタで、美観が損なわれる
-
室外機がビニールで覆われて故障・事故の原因になる
-
足場下の養生不足で、草木や車に塗料が飛ぶ
まとめ
養生作業は、塗装そのものと同じくらい重要なプロセスです。見えない部分で丁寧な仕事をしているかどうかが、施工業者の技術力と誠実さの表れともいえます。
⑦高圧洗浄
高圧洗浄(こうあつせんじょう)とは、外壁塗装や屋根塗装の下地処理において、最初に行う非常に重要な作業の一つで、高圧の水を噴射して、外壁や屋根に付着した汚れ・カビ・コケ・藻・チョーキング粉・旧塗膜などを洗い流す工程です。
高圧洗浄の目的
| 目的 | 詳細 |
|---|---|
| 塗料の密着性を高める | 表面の汚れを取り除くことで、塗料がしっかりと下地に接着します |
| 汚れの再発を防ぐ | カビやコケを根から洗浄することで再発を抑制 |
| 美観の維持 | 塗装前に既存の汚れを除去することで、仕上がりの発色や均一性が向上 |
| 長寿命な塗装のための準備 | 汚れや旧塗膜を残したまま塗装すると、剥がれや膨れの原因になります |
使用する機材と種類
● 高圧洗浄機(業務用)
-
圧力目安:7~15MPa程度
-
エンジン式やモーター式が主流
-
作業には必ず水道と排水経路の確保が必要
● 洗浄方法の種類
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 通常の高圧洗浄(水洗い) | 水のみで汚れを落とす基本的な方法 | 外壁・屋根の一般洗浄 |
| バイオ洗浄(薬剤洗浄) | 専用薬剤でカビやコケを根から分解・除去 | カビ・藻がひどい北側の壁面や屋根 |
| トルネード洗浄 | 回転ノズルで強力に洗浄 | スレート屋根やコンクリート表面など頑固な汚れ向け |
洗浄作業の所要時間
-
一戸建て住宅(外壁・屋根)の場合:約4〜6時間程度
-
汚れの程度、建物の大きさ、屋根の形状などで変動あり
高圧洗浄で落とせるもの
-
チョーキング(白い粉状の劣化した塗料)
-
カビ・コケ・藻
-
砂・泥・ほこり
-
排気ガスの煤煙
-
花粉・黄砂
-
古くなった塗膜(浮いている部分)
高圧洗浄の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 乾燥時間の確保が必要 | 洗浄後は最低でも1日(24時間)以上の乾燥が必要 |
| 強すぎる水圧はNG | 木部や古いモルタルは傷むことがあるため、圧力調整が必要 |
| サッシや室内への水の侵入に注意 | 窓まわりや換気口からの水の侵入を防ぐため、養生との連携が重要 |
| 冬場は凍結・乾きの遅れに注意 | 気温や湿度により施工スケジュールを調整する必要がある |
外壁塗装における高圧洗浄の位置づけ
高圧洗浄は「塗装工事の成功を左右する最初の一歩」です。
この工程が不十分だと、どれほど高性能な塗料を使っても「持ち」が悪くなる原因になります。
「見えない部分をどれだけ丁寧に行うか」が職人の腕の見せ所でもあります。
まとめ
-
高圧洗浄は塗装工事の基礎中の基礎
-
作業の丁寧さで塗装の耐久性・美観が変わる
-
必ず乾燥期間を設けることが重要
⑧バイオ洗浄
バイオ洗浄とは、外壁や屋根などの洗浄作業において、専用の「バイオ洗浄剤(薬剤)」を使って、カビ・コケ・藻・排気ガス汚れなどの「生物由来の汚れ」を根本から除去する方法です。通常の水だけを使った高圧洗浄では落としきれない微細な汚れや再発しやすい菌類を、薬剤の力で徹底洗浄・殺菌する高度な洗浄技術です。
バイオ洗浄の基本構造
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | カビ・コケ・藻などの微生物を根から分解・殺菌 |
| 方法 | 薬剤を外壁に散布し、数分~十数分間反応させた後、高圧洗浄で洗い流す |
| 使用薬剤 | バイオ洗浄液(中性または弱アルカリ性が主流)、除菌・漂白効果あり |
なぜ「バイオ」なのか?
「バイオ(Bio)」とは「生物の」という意味で、生物汚れ(カビ・コケ・藻など)に対応した洗浄手法という意味合いがあります。
汚れの“根”を残すと、見た目はきれいでも再発しやすく、塗料の密着にも悪影響を及ぼすため、根絶やしにするためにバイオ洗浄が使われます。
バイオ洗浄のメリット
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 再発防止 | 微生物の根まで分解・除菌できるため、再発しにくい |
| 塗料の密着力が向上 | 表面だけでなく下地を清浄にすることで、塗料の剥がれ・膨れを防ぐ |
| 見えない汚れにも対応 | 高圧水では届きにくい凹凸部分や小さな隙間にも効果的 |
| 低圧で洗浄可能 | 水圧による外壁の損傷リスクが減る(特にモルタルや木部に有効) |
バイオ洗浄のデメリット・注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| コストが高くなる | 薬剤や手間がかかるため、通常洗浄より費用が上がる傾向(目安:5,000~20,000円程度の追加) |
| 近隣への配慮が必要 | 臭いのある薬剤もあるため、事前に近隣へ説明が必要な場合も |
| 作業時間が長くなる | 薬剤の反応時間・丁寧なすすぎが必要なため、1日がかりになることも |
| 材質によっては使えない場合も | 特殊な天然石や金属面には注意が必要(変色の可能性) |
どんな建物に向いている?
-
北面や日陰でコケやカビがびっしり生えている外壁・屋根
-
築年数が10年以上経過しているモルタル外壁やスレート屋根
-
海沿いや湿気が多い地域の住宅
-
美観だけでなく、塗膜の長寿命化を重視したい場合
バイオ洗浄の施工の流れ(例)
-
足場設置・養生
-
バイオ洗浄剤を全体に散布
-
10~30分ほど薬剤を反応・浸透させる
-
高圧洗浄でしっかりとすすぎ洗い
-
1日以上の自然乾燥
-
塗装工程へ移行
まとめ
-
バイオ洗浄は、「見た目」だけでなく「下地環境」から整えるための洗浄方法
-
高圧洗浄の一歩上を行く施工品質を求める場合に最適
-
長期的に美観・耐久性・防カビ性を保ちたい方におすすめ
⑨清掃作業
外壁塗装における清掃作業(せいそうさぎょう)とは、主に塗装前後に行われる「周囲や施工面の整理整頓・清掃」を指し、安全性・作業効率・仕上がりの品質・顧客満足度を高めるための非常に重要な工程です。
単なる「掃除」ではなく、職人の丁寧さや現場管理のレベルを象徴する仕事であり、プロ意識の現れとも言えます。
清掃作業の分類と役割
① 塗装前の清掃
| 作業内容 | 目的 |
|---|---|
| 高圧洗浄後の汚れや水分の確認 | 汚れが残っていないか再確認 |
| ゴミ・ほこり・蜘蛛の巣の除去 | 塗膜の密着性を高める |
| 外壁以外の清掃(窓・サッシまわり) | 養生や塗装作業の邪魔になる汚れを除去 |
| 足場周辺や敷地の整頓 | 安全に作業を進めるための準備 |
② 塗装中の清掃(中間清掃)
| 作業内容 | 目的 |
|---|---|
| 塗り替えごとのローラーや刷毛の洗浄 | 道具の劣化防止・品質維持 |
| 養生のズレや汚れの拭き取り | 飛散防止と仕上がりの確認 |
| 足場や作業導線の掃き掃除 | 滑りや転倒を防ぐ安全管理 |
| 塗料のこぼれ・付着の即時対応 | 建具・設備への塗料付着を防ぐ |
③ 塗装後の清掃(完工清掃)
| 作業内容 | 目的 |
|---|---|
| 養生材・マスカーの丁寧な撤去 | 建物への傷や塗膜の剥がれを防止 |
| 塗料のはみ出し・垂れの除去 | 美観向上とクレーム防止 |
| 足場解体前の敷地清掃 | ゴミや塗料カス、ビスなどの除去 |
| 隣家や道路の清掃 | 近隣配慮・印象向上 |
| お客様への最終確認前の最終美装 | 引き渡しに向けた仕上げ |
清掃作業が重要な理由
| 理由 | 解説 |
|---|---|
| 塗料の密着性向上 | ゴミやほこりが残っていると、塗膜が剥がれやすくなる |
| 塗装仕上がりの美しさ | 塗りムラ・ゴミ噛みの原因を防止 |
| お客様の満足度アップ | 「きれいにしてくれてありがとう」という声が信頼につながる |
| 事故やトラブルの予防 | 落下物・滑りなどの危険を減らす |
| ご近所への印象配慮 | 道路・駐車場・玄関まわりの清掃は近隣クレームを防ぐ効果あり |
使用する道具例
-
ホウキ、ちりとり
-
雑巾、ウエス
-
スクレーパー
-
水バケツ・中性洗剤
-
ブロワー(送風機)
-
吹き上げ用モップ・乾拭きタオル
-
シンナー(塗料拭き取り用・限定的)
まとめ
外壁塗装における清掃作業は、ただの後片付けではなく、
「品質保証・安全管理・顧客対応」のすべてに関わる重要業務です。
職人の「目配り・気配り・心配り」がもっとも表れる部分とも言え、信頼できる塗装業者ほど、清掃に力を入れているのが実情です。
⑩マスチック
マスチック工法とは、外壁塗装などにおいて使用される特殊な下塗り技法の一つで、専用のローラーを使用して「マスチック材(厚付け用下地調整材)」を厚く塗布し、ひび割れの補修や外壁の凹凸調整、意匠性のある模様づけを行う工法です。
特に、モルタル外壁やALCパネルなどの劣化した外壁に対して、下地を補強しながら塗装の下地を整えるために使われます。
マスチック工法の目的
-
下地の微細なひび割れ(ヘアークラック)の補修
-
塗膜の厚みを確保し、防水性・耐久性を高める
-
凹凸模様をつけて意匠性を演出する
-
経年劣化した外壁を再生・補強する
マスチック工法に使う「マスチック材」とは?
マスチック材は主に「微弾性フィラー」や「弾性下地調整材」と呼ばれるもので、
-
厚塗りができる
-
ひび割れに追従する柔軟性がある
-
吸い込みムラを防ぐ
-
凹凸や欠損を埋める
といった特性を持っています。
使用するローラー:マスチックローラー(砂骨ローラー)
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| マスチックローラー(砂骨ローラー) | 表面に網目や穴が空いており、塗材をたっぷり含ませて「模様」や「厚み」を出すことができる |
マスチック工法の施工方法(一般的な流れ)
-
高圧洗浄・ケレンなどの下地処理
-
シーリング補修・クラック補修
-
マスチック材の塗布(下塗り)
-
マスチックローラーで厚付けし、模様をつけながら塗布
-
-
中塗り・上塗り(仕上げ塗装)
マスチック工法が向いている下地
-
モルタル外壁(クラックが入りやすい)
-
ALCパネル
-
傷みやすいコンクリート面
-
旧塗膜が荒れている外壁
-
意匠性を持たせたい建築外装
マスチック工法のメリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 微細なひび割れをカバー | 下地の補修を兼ねて施工できる |
| 防水性・耐久性が高い | 厚膜により水の侵入を防ぐ |
| 模様・意匠性を出せる | 表面に凹凸をつけられる(吹付の代替にも) |
| 下地の凹凸や劣化を目立たせない | 平滑仕上げよりも補修跡が馴染む |
マスチック工法のデメリット・注意点
| デメリット | 解説 |
|---|---|
| 材料費・手間がかかる | 通常の下塗りより高価で時間がかかる |
| 施工技術が必要 | ローラーの扱い・厚みの均一化に技術がいる |
| 模様が目立つため好みが分かれる | 平滑な外壁を望む人には不向きな場合もある |
まとめ
-
ひび割れ補修 × 下地強化 × 意匠性向上 を同時に実現できる優れた工法
-
外壁の劣化が目立つ建物には特に有効
-
通常の下塗りよりもプロの技術と判断が問われる施工方法
⑪スタッコ
スタッコ吹き(スタッコ仕上げ)とは、外壁仕上げにおける吹き付け塗装の一種で、厚みのある塗材をスプレーガンで外壁に吹き付け、独特な凹凸模様をつける施工方法です。見た目の重厚感や立体感があり、意匠性の高い外観を演出したい場合に用いられる伝統的かつ高級感のある仕上げ方法です。
スタッコ吹きとは?
「スタッコ」とは、本来は石灰やセメント、樹脂などを混ぜた左官材料を意味しますが、日本の塗装業界では「厚膜状の外壁模様吹き付け仕上げ」を指します。
スタッコ吹きは、多孔質ローラーでは表現できない深い凹凸模様を短時間で作れるのが特長です。
スタッコ吹きの施工方法
スタッコ吹きには主に以下の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 仕上がり |
|---|---|---|
| スタッコ吹き放し仕上げ | 吹き付けたまま乾燥させる | 荒々しい質感、骨材感が強い |
| スタッコ押さえ仕上げ | 吹き付けた後、コテやローラーで表面を軽く押さえる | 少し滑らかで落ち着いた印象、和洋どちらにも合う |
使用する材料
-
スタッコ材(厚膜型塗材)
→ アクリル樹脂・シリコン樹脂・セメント系などを主成分とし、骨材(砂・石粒など)を含む -
専用スプレーガン(塗装機)
→ 圧送式またはエアレス式のスプレーで吹き付け
スタッコ吹きのメリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 高級感・重厚感のある外観 | 和風建築・洋風建築どちらにもマッチしやすい |
| 模様が深く、意匠性が高い | 吹き放し・押さえなどで表情が変えられる |
| 塗膜が厚く、耐久性が高い | 厚膜によって外壁の保護性が向上する |
| 下地の傷み・補修跡を隠せる | 凸凹模様で補修跡が目立たない |
スタッコ吹きのデメリット・注意点
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 塗料の飛散が多い | 養生の徹底と近隣への配慮が必要 |
| 施工には熟練技術が必要 | 吹き付け圧・距離・模様の均一さなどの管理が難しい |
| 表面が凸凹しているため汚れが付きやすい | 防汚性の高い塗料やクリア仕上げとの併用がおすすめ |
| 補修時の再現が難しい | 局所的な補修では模様が一致しない可能性あり |
スタッコ吹きが使われる建物例
-
戸建住宅(特に洋風・南欧風の外観)
-
店舗やデザイン重視の外装
-
寺社・伝統建築
-
高級感を演出したい外壁面
まとめ
-
厚膜仕上げ×立体的デザインが魅力の吹き付け工法
-
外壁をただ塗るだけではなく、「魅せる外観」を実現したい人に最適
-
ただし、費用・技術・メンテナンス性を考慮して検討が必要
⑫吹付タイル
吹付タイル(ふきつけタイル)とは、外壁の仕上げ塗装において、タイルのような凹凸模様をつける厚塗りの吹き付け工法で、意匠性・耐久性・防水性を兼ね備えた仕上げ方法です。実際の陶器タイルとは異なり、塗材によって模様をつくり、タイル調に見せることから「吹付タイル」と呼ばれます。
吹付タイルとは?
吹付タイルは、「タイル吹き」とも呼ばれる塗装仕上げの一種で、主に「セメント系」または「合成樹脂系」のタイル吹き塗材をスプレーガンで厚く吹き付け、模様をつけたのち、ローラーやこてで押さえたりせずそのまま仕上げる、または押さえて整えることもあります。
施工方法(主に2種類)
| 工法 | 特徴 | 仕上がり |
|---|---|---|
| タイル吹き放し | 吹き付けたまま乾燥させる | 粒状感のあるザラついた仕上がり(マット調) |
| タイル吹き押さえ(吹き戻し) | 吹き付け後、ローラーで表面を軽く押さえる | 滑らかで艶やかなタイル調の見た目になる |
使用される主な材料
-
合成樹脂エマルションタイル(REタイル)
-
セメント系タイル塗材
-
アクリル・シリコンなどの弾性系吹付タイル材
塗材には「骨材(細かい砂・石など)」が含まれており、立体感ある模様を作ることができます。
吹付タイルのメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 高級感ある外観に仕上がる | 凹凸模様で陰影が生まれ、重厚感が出る |
| 厚膜仕上げで耐久性が高い | 下地の微細なクラックをカバーしやすい |
| デザイン性の自由度が高い | 模様の大きさ・仕上げ方法の組み合わせが豊富 |
| 遮音性・断熱性を高める効果も | 厚塗り塗膜により外部音・熱をある程度緩和 |
吹付タイルのデメリット・注意点
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 塗料の飛散が多い | 近隣住宅や車への飛散リスクがあるため、養生が必須 |
| 施工には高度な職人技が必要 | 模様の均一さや厚みの調整が難しい |
| メンテナンス・補修時に模様再現が難しい | 補修箇所だけ模様が浮く可能性あり |
| 表面の凹凸に汚れが溜まりやすい | 防汚性の高い上塗り材との併用が推奨される |
吹付タイル仕上げが選ばれる建物
-
戸建住宅(特に重厚感や意匠性を求める場合)
-
公共施設・集合住宅
-
店舗や商業施設のファサード
-
ALC・モルタル外壁など
吹付タイルとリシン吹き・スタッコ吹きとの違い
| 比較項目 | 吹付タイル | リシン吹き | スタッコ吹き |
|---|---|---|---|
| 塗膜の厚み | 厚い(1.5〜3.0mm程度) | 薄い(0.3〜0.5mm程度) | 非常に厚い(3〜5mm程度) |
| 意匠性 | タイル調の凹凸が特徴 | ザラザラとした砂壁調 | 重厚な凹凸模様 |
| 耐久性 | 高い | やや低い | 高い |
| 防汚性 | 上塗り材による | やや汚れやすい | 凹凸によっては汚れが溜まりやすい |
まとめ
-
吹付タイルは、塗材でタイル調の立体的な模様を再現する吹き付け塗装仕上げ
-
外壁に重厚感・高級感・耐久性を求める方におすすめ
-
熟練した技術者による丁寧な施工が品質を左右する
⑬吹き付けリシン
吹き付けリシンとは、外壁の仕上げ塗装における吹き付け工法の一種で、リシン材(砂状の骨材を含んだ塗材)をスプレーガンで外壁に吹き付けて、ザラザラとした質感のある表面に仕上げる方法です。
1970年代~1990年代にかけて、戸建住宅や集合住宅で非常に多く採用された仕上げ方法で、現在でもリフォームや部分補修、艶消しでレトロな質感の演出として根強い人気があります。
リシンとは何か?
リシンは以下のような材料を混ぜた塗材です:
-
セメントまたは合成樹脂(アクリル樹脂など)
-
骨材(砂・軽石・寒水石などの細かい粒)
-
顔料(着色材)
-
水や溶剤
これをスプレーガンで外壁に吹き付け、マットで自然な風合いのある表面を作ります。
吹き付けリシンの特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ザラザラとした表面 | 砂壁のような自然な質感が特徴 |
| マットな仕上がり | 光を反射しにくく、落ち着いた印象に |
| 塗膜が薄い(0.3~0.5mm程度) | 軽量な仕上げだが、耐久性はやや劣る |
| 意匠性が高い | 和風建築・洋風建築どちらにも合いやすい |
吹き付けリシンのメリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| コストが比較的安い | 材料費・施工費がローコストで抑えられる |
| 施工が早く、大面積に対応しやすい | 吹き付けで効率的に仕上げ可能 |
| 自然な風合いで落ち着いた外観になる | 住宅街でも違和感のない仕上げ感 |
| 骨材入りで凹凸があるため補修跡が目立ちにくい |
吹き付けリシンのデメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 塗膜が薄く、耐久性がやや低い | 経年劣化が早めで、10年以内で再塗装が必要な場合も |
| 防水性が弱い | 下地処理や上塗り材で補う必要がある |
| 表面の凹凸に汚れが溜まりやすい | 防汚性の低い場合、黒ずみやカビが発生しやすい |
| 飛散が多いため、養生が必須 | 近隣への配慮が必要(特に風の強い日) |
吹き付けリシンの施工手順(一般例)
-
高圧洗浄・下地処理
-
下塗り(シーラーやフィラー)
-
リシン材の吹き付け
-
上塗り(必要に応じてクリアや保護塗装)
他の吹き付け仕上げとの比較
| 項目 | 吹き付けリシン | 吹き付けタイル | スタッコ吹き |
|---|---|---|---|
| 塗膜の厚み | 薄い(0.3~0.5mm) | 中~厚(1.5~3mm) | 厚い(3~5mm) |
| 質感 | ザラザラ・マット | 粒状・重厚 | 凹凸が深く重厚 |
| 耐久性 | △ | ○ | ◎ |
| コスト | ◎ 安い | ○ 中程度 | △ 高め |
こんな建物に使われることが多い
-
昭和~平成初期の戸建住宅・公団住宅
-
ナチュラルで落ち着いた印象を求める建物
-
和風建築、木造モルタル住宅
-
低コストで意匠性を出したいリフォーム物件
まとめ
-
吹き付けリシンは、安価・スピーディ・自然な風合いが特徴の仕上げ方法
-
塗膜が薄いため、耐久性・防水性の確保には上塗りとの組み合わせが重要
-
和風・ナチュラル系デザインを好む方にはぴったり
-
外壁リフォームでは「リシン仕上げからの塗り替え」に対応する施工提案も多い
⑭薬剤清掃
外壁や床などに使用されるタイルにおける薬剤清掃とは、タイル表面に付着した汚れ・エフロ(白華)・カビ・油分・モルタル汚れ・水アカ・シリコン汚れなどを、専用の化学薬剤を使って洗浄・除去する作業です。タイルは耐久性に優れていますが、時間の経過とともに頑固な汚れが蓄積されるため、一般的な水洗いや中性洗剤では落とせない汚れを薬剤で効率的に落とすことが重要です。
タイルに使われる主な薬剤と目的
| 薬剤の種類 | 用途・効果 | 対応する汚れ |
|---|---|---|
| 酸性洗浄剤 | アルカリ汚れを中和・分解 | エフロ・モルタル汚れ・カルシウムスケール |
| アルカリ洗浄剤 | 油分・有機物を分解 | 油汚れ・カビ・黒ズミ・コケ |
| 中性洗剤 | 素材を傷めにくい軽洗浄用 | 軽度な汚れ・日常清掃向け |
| カビ取り剤(次亜塩素酸系) | カビ・藻の除去・殺菌 | タイル目地や湿気の多い場所のカビ |
| シリコン除去剤 | シーリング材の成分除去 | タイルに付着したシリコン汚れや曇り |
薬剤清掃の代表的な手順(例:エフロ除去)
-
現状確認・テスト洗浄
素材の種類や劣化度、薬剤の反応を確認 -
対象部分の濡らし作業(予備湿潤)
酸焼け・薬剤の浸透しすぎを防止するため -
薬剤の塗布
専用ブラシやスポンジで均一に塗布(酸性洗剤等) -
反応時間の確保
5〜10分程度、汚れを浮かせて分解 -
ブラッシング・こすり洗い
汚れをしっかり物理的に除去 -
しっかりと水洗い・中和作業(必要に応じて)
薬剤成分を完全に洗い流すことで素材を守る
注意点
| 注意事項 | 内容 |
|---|---|
| 酸性薬剤は金属に注意 | サッシ・金具などが腐食する恐れがあるため、養生が必須 |
| 薬剤の選定ミスは素材を傷める | 光沢タイルや天然石には使用不可な薬剤もある |
| 作業者の安全対策が必須 | ゴム手袋・保護メガネ・マスクを着用する |
| 強アルカリ・強酸は一般住宅向きでない場合も | 高濃度薬剤はプロ施工向け。DIYでは希釈率に注意 |
薬剤清掃が効果的な汚れの例
| 汚れの種類 | 薬剤清掃の効果 |
|---|---|
| エフロレッセンス(白華) | 酸性洗浄剤で分解・除去 |
| 油・すす汚れ | アルカリ洗剤で分解 |
| カビ・コケ | カビ取り剤で殺菌・洗浄 |
| モルタルや目地のはみ出し | 酸で溶解・除去 |
| シーリング汚れ(曇り) | 専用除去剤でクリーニング |
まとめ:タイルの薬剤清掃とは?
-
一般清掃では落としきれない頑固な汚れや特殊な汚れに対して、適切な薬剤を使って洗浄・除去する専門作業
-
薬剤の種類・希釈・反応時間・対象素材の見極めが重要
-
施工ミスがあると素材劣化・変色・腐食・クレームの原因になるため、専門業者による実施が推奨される
⑮縁切り作業(えんぎりさぎょう)
塗装工事における縁切り(えんぎり)作業とは、特にスレート屋根(カラーベストやコロニアルなど)を塗装する際に行う工程で、塗装後に屋根材同士の重なり部分が塗料で塞がってしまった部分を切り離し、雨水の排出口を確保する作業です。
縁切りは、屋根の「通気性・排水性・防水性」を守る非常に重要な作業であり、省略したり不適切に行うと、屋根裏への雨漏りや塗膜の剥がれなど深刻な施工不良の原因になります。
縁切り作業の目的
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 水の通り道を確保するため | スレート屋根は重なり部分から雨水が内部に入り込む構造のため、出口を確保しないと毛細管現象で雨水が逆流します |
| 湿気や水分を逃がすため | 通気性を確保することで、屋根裏や塗膜内部の結露・腐食を防止します |
| 雨漏り・膨れ・剥がれの防止 | 塗料で隙間が塞がれたままだと、水分が逃げ場を失い、屋根材の浮きや腐食、塗膜不良が起こります |
縁切りの施工方法
① 手作業による縁切り(塗装後に実施)
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 皮スキ(カッター状の工具)を使用 | 屋根材の重なり部に差し込んで、塗膜を切り離す |
| 音と振動に注意が必要 | 作業時にカチカチとした音が発生することがある |
| 手間と時間がかかる | 1枚ずつ確認・処理する必要があるため慎重な作業が必要 |
② タスペーサー工法(塗装前に実施)
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 「タスペーサー」という専用部材を挿入 | 屋根材の重なりにスペーサーを入れて隙間を確保する |
| 塗装後に縁切り作業が不要になる | 省力化・均一性の向上が見込める |
| 標準サイズ:2mm~4mm | 屋根材の反りや密着度により使い分ける |
縁切りが必要な屋根材の種類
| 屋根材 | 縁切りの要否 |
|---|---|
| カラーベスト・コロニアル(スレート) | 必須! |
| 金属屋根(ガルバリウム・トタンなど) | 不要(そもそも隙間なし) |
| 瓦屋根(和瓦・セメント瓦など) | 不要(塗装対象外または構造上隙間あり) |
| アスファルトシングル | ケースによる(重なり構造・通気性による) |
縁切りをしなかった場合のリスク
| トラブル内容 | 原因 |
|---|---|
| 屋根裏への雨漏り | 水の逃げ道がないため、雨水が内部へ浸入 |
| 塗膜の膨れ・剥がれ | 屋根材内部の湿気や水分が滞留し、蒸気圧で剥がれる |
| 内部の木材や下地の腐食 | 長期間の湿気による構造劣化 |
まとめ
-
縁切りは「スレート屋根の塗装において必須の防水対策」
-
作業にはタスペーサー方式と手作業方式があり、屋根の状態によって選択
-
見た目には分かりづらいが、住宅を長持ちさせるために絶対に必要な工程
⑯白木処理
白木処理とは、玄関柱や長押(なげし)、破風板、格子、窓枠、床柱などに使用される「白木(しらき)=未塗装の木部」に対して、汚れ・紫外線・カビ・水分などから木材を保護するために行う洗浄・薬剤処理・保護塗布などの総称です。
和風住宅によく見られる美しい木肌の風合いを保つために欠かせないメンテナンスで、「洗い」「漂白」「防腐・防カビ処理」「保護コート」の工程を含みます。
白木とは?
白木とは、着色・塗装・加工が施されていない天然の木材のことを指します。例えば:
-
玄関の檜柱(ひのきばしら)
-
和室の床柱
-
縁側の柱
-
和風の軒天、長押、格子など
などが該当します。
白木処理の目的
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 美観維持 | 黒ずみやアク(灰汁)、水染みなどを除去し、木の本来の色をよみがえらせる |
| 防カビ・防腐 | 湿気・カビ・腐食から守る処理を施す |
| 撥水効果・紫外線対策 | コーティングにより、木の変色や劣化を抑制 |
| 建物全体の価値維持 | 特に和風建築では、白木の美しさが住宅価値に直結する |
白木処理の主な工程
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| ① 洗い(灰汁洗い) | 漂白剤・アク洗い剤(白木専用)で黒ずみや汚れを除去 |
| ② 中和・水洗い | 漂白剤の成分を中和し、木材を痛めないようにする |
| ③ 乾燥 | 自然乾燥または送風乾燥(十分な乾燥が重要) |
| ④ 防腐・防カビ処理 | 木材保護剤を浸透させて菌や虫を防ぐ |
| ⑤ 撥水・保護仕上げ | 浸透性の保護塗料(白木用ワックスなど)で仕上げる |
使用される薬剤・道具
| 種類 | 用途 |
|---|---|
| 白木洗い用漂白剤(アクロンなど) | 黒ずみやシミの除去 |
| 中和剤(酢酸系など) | 漂白剤の成分を中和 |
| 浸透性防腐剤(キシラデコールクリア等) | 防腐・防虫・防カビ |
| 撥水材・白木保護材(和信クリアなど) | UVカット・水弾き |
| ナイロンブラシ・スポンジ | 洗浄時のこすり道具 |
白木処理が必要になるシーン
-
経年で黒ずんだ玄関柱を元の美しさに戻したい
-
外気にさらされた和風木部(破風・格子など)がカビてきた
-
新築当時のような木の白さを取り戻したい
-
定期的なメンテナンスで木部の寿命を延ばしたい
注意点
| 注意事項 | 内容 |
|---|---|
| プロの知識と技術が必要 | 漂白剤の濃度・反応時間・中和処理を誤ると、木材が変色・脆弱化する |
| 紫外線・雨風の影響が大きい場所は劣化が早い | 早い場合は数年で再処理が必要 |
| 油性塗料や着色後の木部には使えないことがある | 白木専用の処理材でないと逆効果になることも |
まとめ
-
白木処理は、和風住宅の美観を守るための重要な木部メンテナンス
-
黒ずみ・カビ・水染み・紫外線劣化などから木材本来の風合いを取り戻し、長持ちさせる効果
-
工程・薬剤選定・タイミングを誤ると素材を傷める恐れがあるため、専門業者による施工が望ましい