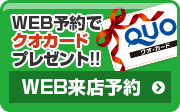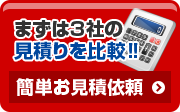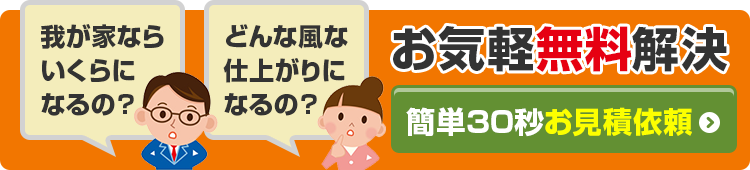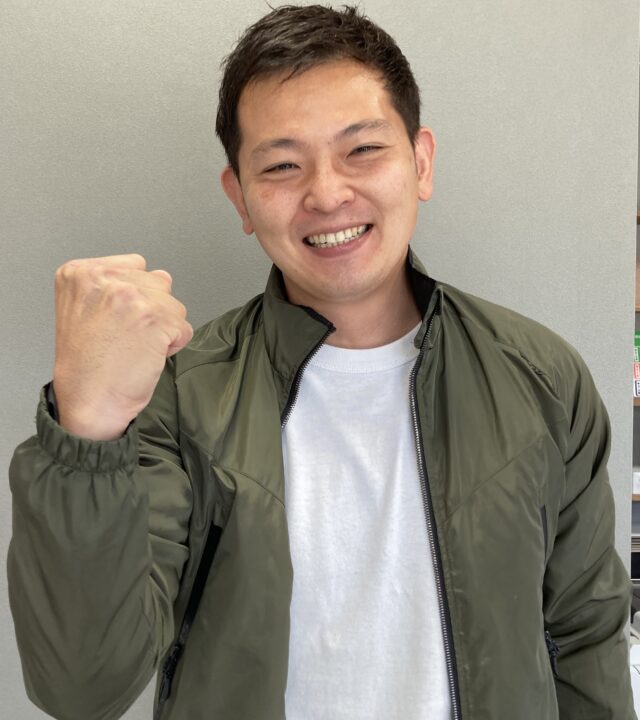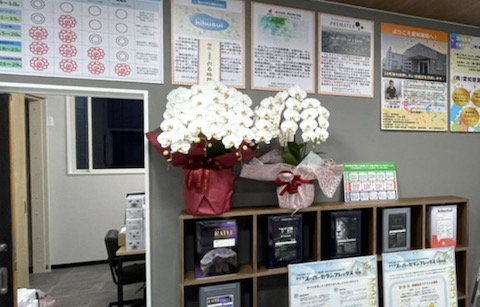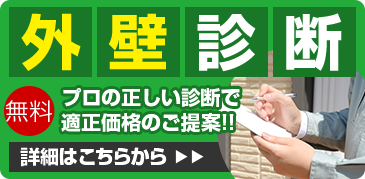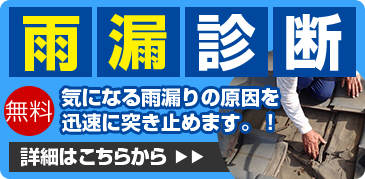用語集その⑤!~劣化編~
2025.09.23 (Tue) 更新
①チョーキング現象
チョーキング現象(チョーキング現象)とは、外壁塗装や屋根塗装の劣化症状のひとつで、手で触ると白い粉がつく現象を指します。主に塗料中の顔料(主に白色顔料である酸化チタンなど)が劣化して表面に浮き出てくることで発生します。
目次
チョーキングの主な原因
-
紫外線・雨風による経年劣化
塗膜が紫外線や雨風にさらされることで、塗料の樹脂成分が分解されて、顔料がむき出しの状態になります。 -
塗料の質や種類
アクリルなどの耐久性の低い塗料ほど、早期にチョーキングが発生しやすいです。逆に、フッ素や無機塗料は発生しにくいです。 -
施工不良・下地処理不良
高圧洗浄や下塗りが不十分だった場合、早期劣化の原因となることがあります。
チョーキングの確認方法
「手で外壁をこする」だけで簡単に確認できます。白い粉が手につくようであれば、それがチョーキングのサインです。
チョーキング現象がもたらすリスク
-
防水性能の低下
-
美観の悪化(色褪せ・粉っぽい外観)
-
カビや苔の発生リスク増加
-
下地の劣化促進(塗膜の剥離など)
チョーキングが起きたらどうすべきか?
-
再塗装のタイミングと判断
チョーキングは再塗装のサインです。発生した場合は、外壁の状態を専門業者に見てもらうのがおすすめです。 -
高圧洗浄による粉の除去
再塗装前にはしっかりとチョーキング粉を洗い流す必要があります。 -
適切な下塗り剤の選定
吸い込みが激しい場合は、フィラーやシーラーの適切な選定が重要です。
チョーキングが起こりやすい場所
-
日当たりが強い南面
-
雨風にさらされやすい面
-
アクリル・ウレタン塗料が使用された外壁
チョーキングを防ぐ方法
-
耐候性の高い塗料(例:無機・フッ素)を選ぶ
-
適切な施工(洗浄・下塗り・上塗りの3工程)
-
定期点検・メンテナンス(5〜10年周期)
②変色・褪色
変色(へんしょく)・褪色(たいしょく)とは、外壁や屋根の塗装表面が本来の色から変化する現象を指します。どちらも経年劣化の代表的な症状であり、見た目の美観の低下だけでなく、塗膜の劣化や機能低下の兆候でもあります。
【変色と褪色の違い】
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 変色 | 塗膜が化学反応や汚れの付着などにより、本来の色とは異なる色に変わること。例:白が黄色っぽくなる、黒が茶色がかるなど。 |
| 褪色 | 紫外線や雨風などの影響で、色が徐々に薄くなる・あせていく現象。例:濃いグレーが薄いグレーに変わっていく。 |
【主な原因】
1. 紫外線による劣化(UV劣化)
-
日光に含まれる紫外線は、塗料の顔料や樹脂を分解します。
-
特に有機顔料(赤・青・緑系)は劣化しやすい。
2. 雨風や湿気
-
酸性雨や塵埃による化学反応で変色が起こる。
-
北面など湿気の多い場所では苔・カビによる変色も。
3. 排気ガス・工場煙などの外的要因
-
交通量の多い場所や工場の近くでは大気汚染物質が色調変化を引き起こすことも。
4. 塗料の選定ミス・品質不足
-
耐候性が低い塗料(例:アクリル)を使うと早期に褪色・変色しやすい。
【見分け方と兆候】
| 現象 | 兆候 |
|---|---|
| 変色 | 一部の場所だけが違う色に見える/黒ずみ・黄ばみ・緑がかりなど |
| 褪色 | 全体的に色が薄くなっている/色がぼやけた印象になる/ツヤが消える |
【変色・褪色が進行すると】
-
建物の見た目の印象が悪くなる
-
塗膜の保護機能(防水・防汚など)が低下
-
劣化が進むと再塗装費用が増大するリスクも
【対策・防止策】
-
高耐候性塗料の選定
-
無機塗料・フッ素塗料・シリコン塗料など
-
ラジカル制御型塗料もおすすめ
-
-
定期的な点検とメンテナンス
-
5~10年周期で外壁診断を行う
-
-
変色しにくい色選び
-
有機顔料よりも無機顔料(白・黒・グレー系)を使うと褪色しにくい
-
-
日当たり・風通しの調整(可能であれば)
-
直射日光が強い面は対策を講じる
-
③クラック
クラックとは、「ひび割れ」のことで、外壁や屋根、基礎、コンクリート部分、モルタル・サイディングなどに発生する建物の劣化現象のひとつです。特に外壁塗装の点検・診断においては重要なチェックポイントとされます。
クラックの種類
クラックにはいくつかの種類があり、それぞれ原因や補修方法が異なります。
| クラックの種類 | 特徴・原因 |
|---|---|
| ヘアークラック | 幅0.3mm未満、浅く細かいひび割れ。塗膜やモルタル表面の経年劣化・乾燥収縮が主な原因。 |
| 構造クラック | 建物の構造に影響を与える深刻なひび割れ。幅0.3mm以上。基礎の沈下や地震、不同沈下が原因のことも。 |
| 乾燥クラック | モルタルやコンクリートが乾燥する際の収縮によって起きる。施工初期によく見られる。 |
| 縁切れクラック(開口クラック) | 窓枠やドア周辺など開口部に発生。建物の動きや伸縮に伴い割れやすい部位。 |
| 縦クラック・横クラック | 板間や外壁パネルの継ぎ目、ジョイント部分、サイディング目地部などに見られる。 |
クラックの見分け方と目安
| 幅の目安 | 状態 | 補修の必要性 |
|---|---|---|
| 0.3mm未満 | ヘアークラック | 緊急性は低いが塗り替え時には対応推奨 |
| 0.3〜1.0mm | 軽度な構造クラック | 早期補修を検討すべき |
| 1.0mm以上 | 構造上の問題が懸念 | 早急な専門業者による調査・補修が必要 |
※クラックスケールなどの測定ツールで幅をチェックすることが一般的です。
クラックを放置すると?
-
雨水の侵入 → 下地材の腐食・カビ発生
-
シロアリ被害の原因に
-
建物の耐久性低下・構造材の劣化
-
室内の湿気・断熱性低下につながることも
クラックの補修方法
| クラック種類 | 補修方法 |
|---|---|
| ヘアークラック | 微弾性フィラー塗布/上塗り再塗装 |
| 幅0.3mm以上のクラック | Uカットシーリング充填/エポキシ樹脂注入 |
| 構造クラック | 専門業者による構造補強・外壁張り替え |
外壁塗装とクラック補修の関係
外壁塗装を行う前には必ずクラックの有無を点検し、事前に補修してから塗装を行うことが基本です。補修を怠ると、塗膜内部に再び水が侵入し、塗装の早期剥がれや内部腐食の原因となります。
④爆裂
爆裂(ばくれつ)とは、鉄筋コンクリート構造の外壁や基礎、梁などで発生する深刻な劣化現象で、内部の鉄筋が膨張してコンクリートを内側から押し出し、ひび割れや破片の剥落(はくらく)を引き起こす現象を指します。
爆裂の概要
主な発生メカニズム
-
コンクリート内部の鉄筋が酸化(錆びる)
-
鉄が酸化して体積が約2〜3倍に膨張
-
周囲のコンクリートに強い圧力がかかる
-
コンクリート表面が割れる・剥がれる(爆裂)
発生しやすい場所
-
鉄筋コンクリート造(RC造)建物の外壁・基礎・梁・柱
-
打継ぎ部・開口部周辺(窓の角など)
-
雨水が染み込みやすい箇所(防水不良部位やひび割れがあるところ)
-
海沿いや工場周辺など塩害や酸性雨の影響が強い地域
爆裂の兆候
-
コンクリート表面に浮きや盛り上がりが見える
-
小石状の破片が落下する
-
赤茶色のサビ汁が染み出している
-
ひび割れの中に金属が見える
放置するとどうなる?
-
破片の落下事故(通行人・車両への被害)
-
鉄筋の断面減少 → 耐震性の低下
-
建物の構造的な安全性に重大な影響
-
雨水や湿気の侵入による内部腐食の進行
補修方法
| 状態 | 補修方法 |
|---|---|
| 軽度な浮き | 表面の浮き除去 → 防錆処理 → 補修モルタル → 塗装 |
| 鉄筋露出あり | 鉄筋ケレン(錆落とし) → 防錆塗布 → 欠損部補修(樹脂モルタル等) |
| 大規模爆裂 | 範囲が広い場合は打ち替えや外壁パネルの張替えが必要 |
予防策
-
定期点検・打診調査(タイルやコンクリートの浮き確認)
-
塗装や防水工事による浸水防止
-
中性化抑制に効果のある塗料選定(中性化防止塗料)
-
ひび割れ(クラック)を放置しないこと
⑤雨漏り
雨漏り(あまもり)とは、屋根・外壁・ベランダ・サッシなど建物の外部から雨水が建物内部に浸入する現象です。天井からポタポタと水が垂れるような目に見える症状だけでなく、目に見えない箇所から静かに侵入しているケースもあり、建物の構造劣化や健康被害につながる重大な問題です。
雨漏りの主な発生箇所
| 発生箇所 | 原因の例 |
|---|---|
| 屋根(瓦・スレート・板金) | 割れ・ズレ・錆び・施工不良 |
| 外壁(モルタル・サイディング) | クラック・コーキング劣化 |
| ベランダ・バルコニー | 防水層の劣化・排水口詰まり |
| サッシまわり | シーリング劣化・取付不良 |
| 天窓・換気口・配管まわり | 隙間・取付不良・老朽化 |
雨漏りのサイン(兆候)
-
天井や壁紙のシミ・変色
-
室内でカビ臭さ・湿気
-
雨が降った後に窓枠まわりに水が溜まる
-
クロスの剥がれやフローリングの浮き
-
屋根裏での水音・シミ
雨漏りの調査方法
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 目視点検 | クラックや隙間の確認。初期診断に有効。 |
| 散水調査 | 実際に水をかけて浸入口を特定。時間と技術が必要。 |
| 赤外線サーモグラフィ | 水分のある場所を温度差で検出。非破壊で可能。 |
| 発煙調査・色水調査 | 室内から煙や色水を流して侵入口を確認。 |
雨漏りを放置すると?
-
木材腐食(柱・梁が弱くなる)
-
断熱材の機能低下
-
シロアリ被害の誘発
-
カビ発生 → アレルギーや健康被害
-
建物の資産価値低下
雨漏りの対策・補修方法
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 屋根材のズレ・割れ | 屋根材交換・差し替え・防水シート補修 |
| クラック | 補修材充填+外壁再塗装 |
| シーリング劣化 | 打ち替え or 打ち増し施工 |
| 防水層劣化 | ウレタン防水・FRP防水・シート防水など再施工 |
雨漏りと塗装の関係
-
外壁や屋根塗装は防水機能の維持に直結します。
-
雨漏りがある状態での塗装は根本解決にはならず、事前の補修が必須です。
-
塗装の際は防水・シーリング・下地補修をセットで提案することが重要です。
⑥サビ
サビ(錆)とは、金属が酸素や水分、塩分などと化学反応を起こして腐食し、劣化していく現象です。特に外壁や屋根、鉄部(手すり・庇・配管・ベランダの笠木など)において、見た目の劣化・構造上の劣化・建物全体の寿命短縮につながる非常に重要な劣化症状のひとつです。
サビの発生メカニズム
サビは主に次のような化学反応で発生します。
-
鉄(Fe)+ 酸素(O₂)+ 水(H₂O)
→ 酸化鉄(Fe₂O₃)= 赤茶色のサビ
この反応が進行することで、金属が腐っていく=錆びていくという状態になります。
サビの種類
| 種類 | 特徴・発生原因 |
|---|---|
| 赤サビ(酸化鉄) | 最も一般的。鉄部の表面に出る赤茶色のサビ。 |
| 白サビ(酸化亜鉛) | トタンや亜鉛メッキ鋼板などに発生。白っぽい粉状。 |
| 黒サビ | 鉄の高温酸化でできる安定した被膜。悪性ではない。 |
| 緑青(ろくしょう) | 銅や真鍮に発生する緑色のサビ。美観的には味わいとも。 |
サビの主な発生箇所(住宅・外装)
-
トタン屋根・ベランダの笠木
-
鉄製階段・手すり
-
スチール製のシャッター・庇・水切り
-
エアコン配管のカバー・室外機台
-
アンテナや看板の支柱
サビを放置すると…
-
腐食が進行し、穴あき・崩壊・落下の危険性
-
外壁や屋根にサビ汁が流れて美観を損ねる
-
建材の交換が必要になり、補修費用が高額化
-
シロアリ被害や雨漏りを誘発することも
サビ対策・補修方法
| 状態 | 対応方法 |
|---|---|
| 表面のサビ(軽度) | ケレン作業 → 錆止め塗装 → 上塗り |
| サビが進行している場合 | サビ転換剤+錆止め → 補修塗装 |
| 穴が開いている | 補修材や金属板で成形 → 塗装/場合により部材交換 |
※ケレンとは、サビや旧塗膜をヤスリや工具で除去する作業です(1種〜4種ケレンが存在)。
サビ止め塗料とは?
-
金属表面に防錆層を形成する塗料
-
代表的な成分:エポキシ系、フェノール系、亜鉛リッチ系
-
塗装前には必ず下地処理(ケレン)が必須
-
上塗りは耐候性・耐水性のある塗料を推奨(ウレタン・シリコンなど)
⑦剥離
塗膜の剥離(とはくのはくり)とは、塗装された塗膜が下地から浮いたり、めくれたり、はがれてしまう現象を指します。外壁や屋根、鉄部、木部など塗装されたあらゆる箇所で発生する劣化症状のひとつで、防水性・美観・耐久性の低下につながります。
【塗膜とは?】
「塗膜」とは、塗料を塗った後に乾燥・硬化してできる保護の膜のことです。塗膜は、建物の外壁や屋根を紫外線・雨風・汚れ・サビ・カビなどから守るバリアの役割を果たしています。
【塗膜の剥離が起こる主な原因】
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 下地処理の不良 | 高圧洗浄不足・ケレン不足・ホコリや油分残留による密着不良 |
| 下塗り(プライマー)不足・不適切な塗料選定 | 下塗りなし、または素材と塗料の相性不良による密着不良 |
| 経年劣化 | 紫外線や雨風によって塗膜自体が劣化・硬化・脆弱化 |
| 湿潤状態での施工 | 雨上がり・結露など、水分を含んだ下地への塗装 |
| 素地の動き・膨張収縮 | 木材やモルタルなどが動くことで、塗膜が追従できず割れる/浮く |
| 旧塗膜の劣化 | 上塗りする際に、前回の塗膜が傷んでいると新しい塗膜が密着しにくい |
【塗膜剥離の見分け方】
-
外壁や屋根の一部がめくれ上がっている
-
指でこするとペリッと表面がはがれる
-
表面に膨らみ・浮き・フクレがある(前兆)
-
塗料片が粉状やフィルム状に剥がれる
【塗膜剥離を放置するとどうなる?】
-
下地がむき出しになり、雨水の侵入やサビ・腐食の進行
-
建物の劣化スピードが加速
-
外観が著しく悪化し、資産価値も低下
-
塗装の意味(防水・保護)がゼロになる
【塗膜剥離の補修方法】
| 状態 | 対応方法 |
|---|---|
| 部分剥離(軽度) | 剥離部を除去 → ケレン → 下塗り → 上塗り |
| 広範囲の剥離 | 全面の塗膜を除去(ケレンまたは剥離剤) → 下地調整 → 再塗装 |
| 下地の劣化あり | 素地補修(クラック補修・パテ埋めなど)→塗装工程へ |
【塗膜剥離の予防対策】
-
高圧洗浄やケレンなどの下地処理を徹底
-
下地と塗料の相性確認(素材別のプライマー選定)
-
適切な気温・湿度で施工を行う
-
耐候性・密着性の高い塗料を使用
-
定期的な点検と再塗装の時期を守る(10年目安)
⑧ブリード
ブリードとは、塗装後の仕上がり面に
下地やシーリング材などに含まれる成分がにじみ出て、汚れ・変色・ベタつきなどを引き起こす現象を指します。
主に外壁塗装の仕上がり品質を大きく損ねる美観上の不具合であり、再塗装時やシーリング上の塗装でよく発生します。
ブリード現象の例
-
白い壁に黒っぽいにじみが出てきた
-
コーキング(シーリング)上だけ汚れたような筋が残っている
-
塗った直後はきれいでも数週間〜数ヶ月後に変色してくる
-
表面がベタベタしている/ほこりが付着しやすい
ブリードが起こる原因
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 可塑剤のにじみ出し | シーリング材に含まれる可塑剤(柔らかくする添加剤)が塗膜ににじみ出る |
| 下地との相性不良 | 特にウレタン・シリコン系シーリング材の上に塗装した場合 |
| 下塗り・プライマーの未使用/選定ミス | 専用プライマーやブリード対策塗料を使わないと発生しやすい |
| 旧塗膜に含まれる有機成分の移行 | 古い塗膜の中の油分や色素が新しい塗膜へ浸出することもある |
発生しやすい箇所
-
シーリング材の上(特に打ち替え・打ち増し箇所)
-
モルタル外壁のヘアークラック補修跡
-
雨樋や鉄部との接合部
-
サイディングの目地部
ブリードを放置すると?
-
見た目が悪く、美観を著しく損なう
-
塗り替え直後なのに「失敗感」や「老朽化感」が出る
-
再塗装しても同じ症状が再発する可能性が高い
-
汚れが定着しやすく、長期的に清掃が困難になる
ブリード対策・予防方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ノンブリードタイプのシーリング材使用 | 可塑剤がにじまないよう設計されたシーリング材 |
| ブリードオフプライマーを使用 | 可塑剤を遮断する専用プライマーをシーリングの上に塗布 |
| 下塗り材の選定を適切に | 弾性対応・ブリードブロックタイプの下塗り材を選ぶ |
| 可塑剤の少ない高性能材料選び | 弾性シリコン・変性シリコンなど高耐候性シーリングの使用 |
再発防止のための塗装工程例(シーリング上)
-
シーリング施工(ノンブリードタイプ推奨)
-
乾燥養生期間の確保(2〜3日)
-
専用ブリードオフプライマー塗布
-
適切な下塗り塗布
-
上塗り2回塗布(ブリード対応塗料)
⑨エフロエッセンス
エフロエッセンスとは、コンクリート・モルタル・レンガ・ブロックなどの表面に白い粉や結晶が浮き出てくる現象です。
「白華(はっか)現象」とも呼ばれ、外壁塗装やタイル工事などの現場で美観を損ねる代表的な劣化・変質症状のひとつです。
エフロエッセンスの正体
コンクリートやモルタルなどのセメント系建材には、水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)などのアルカリ性成分が含まれています。
-
建材内部の水に成分が溶け出す
-
それが毛細管現象で表面に移動する
-
表面で水分が蒸発
-
炭酸カルシウム(CaCO₃)や塩類が結晶化して白く残る
エフロエッセンスの見た目と特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 色 | 白色(まれに灰色) |
| 形状 | 粉状・結晶状・モヤモヤした汚れ |
| 質感 | 手でこするとパウダー状になることが多い |
| 発生箇所 | ブロック塀・擁壁・基礎・タイル目地・外壁のモルタル部など |
発生条件・原因
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 水分の過剰供給 | 雨水・湿気・施工時の水分残留など |
| 通気・排水不良 | 内部にたまった水分が逃げにくい構造 |
| 材料の未乾燥・養生不良 | セメントが完全に硬化する前に雨にあたるなど |
| 目地・隙間の防水不良 | 隙間から水が浸入し、内部の成分を押し出す |
エフロを放置するとどうなる?
-
外観が非常に悪くなる(白い汚れが広範囲に出る)
-
タイルや目地の剥離・劣化を招く
-
カビや苔の発生を助長
-
建材の中性化(鉄筋コンクリートの劣化)が進行する可能性
エフロエッセンスの除去方法
| 方法 | 対応内容 |
|---|---|
| 軽度の場合 | 乾いたブラシでこすって除去 or 水洗い |
| 中程度 | 酸性洗浄剤(クエン酸・専用除去剤)で洗浄し水で中和・洗い流す |
| 再発防止策 | 防水材の塗布・通気性の確保・防水層の見直し |
再発防止対策
-
透湿防水材・撥水剤の使用
-
目地やクラックの補修・シーリング施工
-
雨仕舞(排水・傾斜設計)の改善
-
セメント系部材の施工時には十分な乾燥・養生
⑩コーキングの破断
コーキングの破断(はだん)とは、サイディング外壁などの目地や継ぎ目に施工されたシーリング材(コーキング)が裂けたり、断ち切れた状態になる現象です。
これは外壁塗装や建物メンテナンスにおいて非常に重要な劣化サインであり、雨水の侵入や外壁材の劣化を引き起こす重大なトラブルの原因となります。
コーキング(シーリング)とは?
-
外壁の目地(ボードとボードの隙間)やサッシまわりなどの隙間を埋めるゴム状の防水材。
-
主な役割:
-
防水
-
伸縮追従(建物の動きを吸収)
-
気密・断熱性能の確保
-
美観の維持
-
コーキング破断とは?
コーキングが引き裂かれるように縦に割けて、目地の内部が見える状態を「破断」と呼びます。
これは、表面の劣化(ひび割れや肉やせ)よりも深刻な症状です。
コーキング破断の見た目の特徴
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 中央から縦に裂けている | 両側の外壁材からシーリングが引っ張られ断裂している |
| 隙間ができて奥が見える | 目地の底が見える場合も |
| 表面ではなく内部から割けている印象 | 経年劣化の最終段階に近い |
なぜ破断が起こるのか?
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 経年劣化 | 紫外線・雨風の影響により弾力性が失われ、硬化・脆化 |
| 目地の伸縮追従に限界がきた | 建物の揺れや温度変化による膨張収縮にシーリングが耐えられなくなる |
| 三面接着 | シーリングが底面にもくっつくことで、伸び代がなくなり割れやすくなる(※プライマー施工不良など) |
| 施工不良・材料不適合 | 不適切な材料選定や下地処理不足、厚み不足など |
放置するとどうなる?
-
雨水が目地内部に侵入 → 外壁の裏面が濡れる
-
サイディングの反り・腐食・カビ発生
-
躯体の断熱材・柱などの劣化・腐食
-
最終的には雨漏りや外壁材交換など大規模工事に発展
補修方法
| 状態 | 対応方法 |
|---|---|
| 破断のみ・下地は健全 | コーキング打ち替え(旧材完全撤去→プライマー塗布→充填) |
| サイディングが反っている | 下地補修・サイディングのビス留め補強+コーキング打ち替え |
| 壁全体が劣化 | 外壁塗装や張替えを併用検討 |
破断を防ぐためには?
-
高耐久シーリング材(変性シリコン・オートン・サンライズ等)を使用
-
打ち替え工事は10年前後で定期的に実施
-
三面接着を避けるために“バックアップ材”を正しく使用
-
塗装との相性を確認(ノンブリードタイプなど)