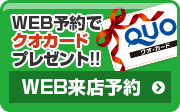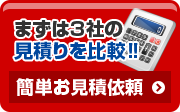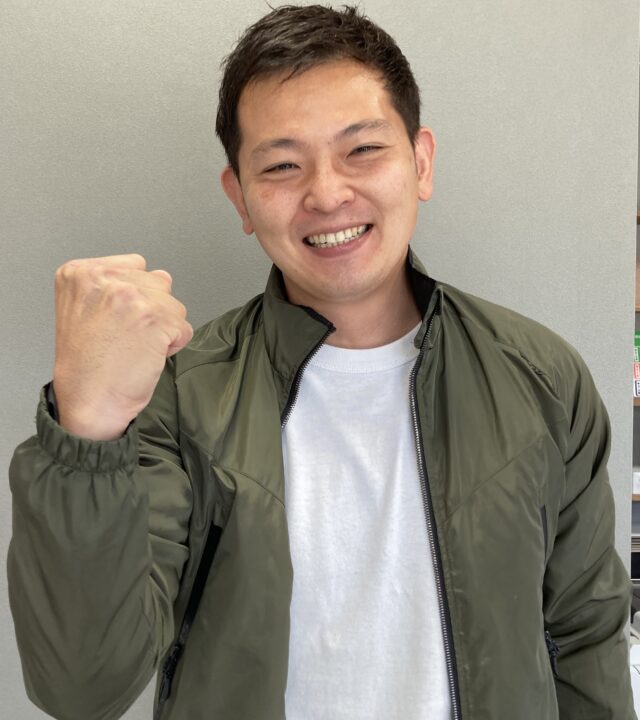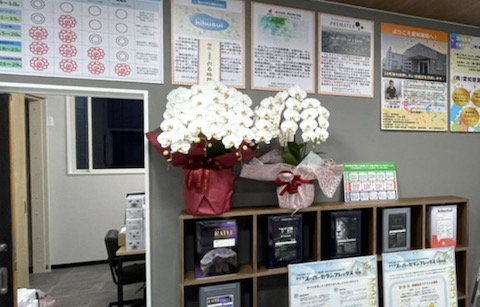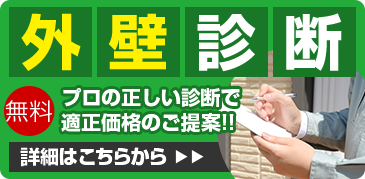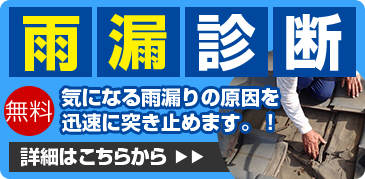【岡崎市】~一条工務店の艶消し塗料での外壁塗装・コーキング工事の完了確認に伺いましたの巻~艶消し塗料はスーパーセランG4
岡崎市・幸田町の外壁塗装・屋根塗装・防水工事専門の愛知建装の三浦です。 あなたへより良い塗装工事のために、おいしい食パンを届けて頑張っております!! 外壁塗装・屋根塗装などその他の工事はこちら!! 岡崎市・幸田町の皆様、こんにちは! 本日の熱量がハンパないブログはこちら! とっても納得のお見積もりをご希望の方はこちら!! 今回は岡崎市のお客様のお宅に外壁塗装の工事完了確認へ行きました! さっそく見ていきましょう!! ~今日のもくじ~ ①スーパーマットな水性無機塗料『スーパーセランG4』【岡崎市の一条工務店の外壁塗装・付帯塗装の完了確認編】 ②艶感なし・ムラ感なし!【岡崎市の一条工務店の外壁塗装・付帯塗装の完了確認編】 ⓷スーパーマット【岡崎市の一条工務店の外壁塗装・付帯塗装の完了確認編】 ④マットとスーパーマット【岡崎市の一条工務店の外壁塗装・付帯塗装の完了確認編】 ⑤水切り板金【【岡崎市の一条工務店の外壁塗装・付帯塗装の完了確認編】 ⑥擁壁【岡崎市の一条工務店の外壁塗装・付帯塗装の完了確認編】 ①暖色系のお屋根が温かみを醸し出す一条工務店のお住まい! イメージを壊さず、丁寧に塗装工事を行いました!! ②お客様のご希望により外壁塗装は艶なしでの施工! 使用した塗料はあの無機塗料のパイオニア・ダイフレックス社(旧・興和化学)の『スーパーセランG4』!! この艶感のなさでかなりの耐久性を保持するとても良い外壁用塗料なんです! ③通常は対候性・耐久性を確保するために、艶感を若干残すのですが、この塗料の一番のポイントは『艶感のなさ』なんです! 『え?艶なしなんだから艶なんてなくて当たり前でしょ?』・・・そう思われたあなた! 実は艶消しというものの、今まで使用してきた塗料は若干の艶感が出ていたんです! それらに比べてこちらの『スーパーセランG4』は鏡面光沢度が4%と今まで使用した塗料よりも艶感がないんです! とっても素敵!!! ④幕板などの塗料は最強無機塗料の『キクスイラーテル』! こちらも艶感を抑えた3分艶(70%艶感を落としたもの)を塗っているのですが、『キクスイラーテル』マットな艶感と『スーパーセランG4』のスーパーマットが圧倒的にナイス!! ⑤外壁塗装だけでなく水切り板金もほら、ステキ! ⑥擁壁も塗装させていただきました! ジョリパットの質感がとてもいいですね! 外壁塗装とマッチしてます! いい感じの仕上がりにお客様もとても喜んでいただけました! K様、ご友人・お知り合いにと塗装工事をお考えの方が見えたら是非、ご紹介お願いいたします!! 愛知建装で見積もりを取ってもらうメリットは、見積書で一番重要な『塗料の良し悪し』をわかりやすくエスコートできること! 他社さんの営業マンより圧倒的塗料の情報量を有した、自称『塗料のプロフェッショナル・オブ・プロフェッショナル』の三浦が有益な情報・お話をさせて頂きます!! 当然、愛知建装で施工して頂きたいですが、せっかくご縁をいただく以上、愛知建装で施工をしなくてもいい工事を行って欲しいという強い気持ちで頑張って提案しております!! 丁寧な工事を心掛けて…、これこそが『愛知建装クオリティー』!! このように当社のセールスポイントは他社を圧倒する丁寧さです!! 当社はお客様のために、国家資格である一級塗装技能士が施工・管理を行い、徹底的に外壁塗装・屋根塗装工事を行っております。 愛知建装は外壁塗装・屋根塗装・防水工事以外の工事でも、瓦屋根の漆喰工事・コーキング工事・板金工事などの工事を安心・安全・お値打ち価格にて承っております!! ただ単純に外壁塗装工事だけではなく、ひと手間を惜しむ業者さんがほとんどの昨今、愛知建装では長く持たせるためのひと手間を惜しみません!! お客様の『ありがとう』が私たちのエネルギーです! しつこい営業は一切なし!無料お見積もりはこちら!! それ以外のことでも当社では経験豊富な専任スタッフによる、的確かつ丁寧な説明でお客様にご安心頂ける提案をしております。 お客様の利益のために、安心・安全を心がけて日々精進して参ります!! 些細なことでも外壁塗装・屋根塗装・防水工事に関しましては専門業者である愛知建装へお任せください! 岡崎市の一条工務店のお住まいのオーナーさんが、艶消し塗料での外壁塗装工事を依頼する際に、無機塗料での外壁塗装と火災保険の申請が得意な愛知建装に依頼するメリットとは 岡崎市で一条工務店の住宅にお住まいのオーナーさまの中には、外壁の色あせや汚れ、艶のムラが気になり、外壁塗装工事を検討している方も多いでしょう。一条工務店の住宅は高気密・高断熱性能に優れていますが、外壁材の性質上、艶のある塗料が浮いてしまう、高級感を損ねるというご相談をよくいただきます。 そこでおすすめなのが、艶消し塗料による外壁塗装です。落ち着いた質感で、高級住宅の風合いを損なわず、美しく仕上げることができます。 本記事では、岡崎市で無機塗料「スーパーセランG4」を使用した艶消し仕上げの外壁塗装、そして火災保険の申請サポートにも強い「愛知建装」に依頼するメリットを詳しくご紹介します。 1. 一条工務店の住宅に多い外壁の特徴と塗装の課題 一条工務店の外壁は、「ハイドロテクトタイル」や「窯業系サイディング」が多く採用されています。どちらも耐久性が高い一方で、施工の際には素材特性を理解した塗装技術が求められます。 ● 一条工務店の外壁でよくあるお悩み 外壁の艶が強く出すぎて高級感が失われた 経年で目地シーリングがひび割れている タイルやサイディングの一部にコケ・黒ずみが発生 紫外線で色ムラ・ツヤムラが目立つ これらの問題を改善するためには、艶を抑えた無機塗料での再塗装が最適です。 (関連記事:外壁塗装と屋根カバー工法を愛知建装で同時に施工する利点とは) 2. 艶消し塗料の魅力 ― 上品で落ち着きのある仕上がり 一般的な外壁塗料には「艶あり」「3分艶」「5分艶」「艶消し」などの種類があります。中でも一条工務店の住宅のようにデザイン性が高い家には、艶消し塗料が非常に人気です。 ● 艶消し塗料のメリット 光の反射を抑え、落ち着いたマットな質感を実現 高級住宅や和モダン住宅との相性が抜群 経年によるツヤムラが出にくく、長期間美観を維持 外壁の凹凸や素材感を活かすナチュラルな仕上げ 愛知建装では、艶を抑えながらも耐久性を確保できる無機塗料「スーパーセランG4」を採用し、美しさと長持ちを両立した施工を行っています。 3. 無機塗料「スーパーセランG4」で実現する最上級の艶消し仕上げ 「スーパーセランG4」は、無機塗料の中でもトップクラスの性能を誇る高耐久塗料です。通常、艶を抑えると耐久性が下がる塗料が多いのですが、G4は艶消しでも20年以上の耐候性を実現しています。 ● スーパーセランG4の特長 無機+有機ハイブリッド構造で高耐久と柔軟性を両立 超耐候性(20年)で再塗装回数を削減 雨で汚れを落とすセルフクリーニング機能 紫外線・酸性雨・塩害にも強く、岡崎市の環境に最適 艶消しタイプでも変色・退色がほぼゼロ また、スーパーセランG4は一条工務店のような高断熱サイディングや外壁タイル住宅にも対応可能。質感を保ちながら、長期間にわたって外観の美しさを維持できます。 (関連記事:愛知建装が無機塗料でアパートの外壁塗装を施工するメリットとは) 4. 一級塗装技能士による丁寧な施工と艶調整技術 外壁塗装で最も重要なのは、「塗料の性能を最大限に引き出す施工技術」です。愛知建装では、国家資格である一級塗装技能士が現場に立ち会い、塗料の希釈率・塗布量・乾燥時間を厳密に管理しています。 ● 施工工程の流れ 外壁洗浄:高圧洗浄で汚れ・コケ・旧塗膜を除去 下地処理:ひび割れやシーリングの劣化を補修 下塗り:素材と塗料を密着させる専用プライマーを使用 中塗り・上塗り:スーパーセランG4を2回塗り重ね、均一な膜厚を形成 艶調整:外観・照明・環境に合わせて艶感を最終調整 一条工務店の外壁素材や建築デザインを理解した上で、最も自然な艶感に仕上げる塗装が可能です。 5. 火災保険の申請で補修費を軽減できる可能性 実は、外壁や屋根の劣化の中には「自然災害による損傷」として火災保険の申請が認められるケースがあります。 ● 火災保険で補償される主な事例 台風・突風で外壁や軒天が破損・剥離した 雹(ひょう)による外壁のへこみ・傷 飛来物によるサイディングのひび割れ 雨漏りの原因となるシーリング破断や棟板金の浮き 愛知建装では、岡崎市で多数の申請サポート実績があり、保険会社提出用の報告書・見積書の作成も無料で行っています。 ● 申請サポートの流れ 無料現地調査(損傷箇所の写真撮影) 損害報告書・修繕見積書の作成 保険会社への申請サポート 承認後、外壁塗装工事を実施 保険の適用により、実質自己負担を抑えて高品質塗装が可能になる場合があります。 (関連記事:愛知建装が足場無料期間のキャンペーン中に無料見積もりを取るメリットとは?) 6. 無料見積もりで現状を「見える化」 愛知建装では、岡崎市全域で無料見積もりを実施しています。経験豊富な外装診断士が、劣化状況を写真付きでわかりやすく説明し、最適なプランを提案します。 ● 無料見積もりの流れ 現地調査のご予約 外壁・屋根・シーリングの状態をチェック 写真付き診断書を作成 スーパーセランG4の艶消し・3分艶など複数プランを比較提案 塗料の違いや仕上がりイメージもサンプルで確認できるため、初めての方でも安心です。 7. 艶消し塗装に向いている住宅デザイン 艶消し塗料は、特に以下のような住宅におすすめです。 一条工務店のモダン住宅(アイスマート・グランセゾンなど) 和モダン住宅・木目調外壁の家 グレー・ベージュ・ブラック系の落ち着いた配色 外壁のデザイン性を高めつつ、経年変化を感じさせない上品なマット感を演出します。 また、屋根やサッシなどの付帯部も同時に艶感を統一することで、全体的な仕上がりにまとまりが生まれます。 8. 無機塗料の耐久性が岡崎市の環境に適している理由 岡崎市は、夏の高温多湿・冬の寒暖差・台風の影響と、外壁にとって過酷な環境条件が揃っています。そのため、無機塗料の高耐候性と防汚性能が特に効果を発揮します。 紫外線による塗膜劣化を防ぐ 雨水が汚れを流す「セルフクリーニング効果」 コケ・藻・カビの発生を抑制 酸性雨や塩害にも強く、沿岸部でも安心 これにより、一度の施工で20年以上美観を維持できる長寿命外壁を実現します。 9. アフターメンテナンスと保証内容も充実 愛知建装では、施工後もお客様が安心して暮らせるよう、長期保証と定期点検制度を整えています。 1年・3年・5年の定期点検 無機塗料施工にはメーカー保証+自社保証をダブルで付帯 不具合が発生した場合は最短即日対応 地元密着の施工店として、施工後も長く寄り添うサポート体制を築いています。 10. まとめ ― 一条工務店の外壁塗装は艶消し+無機塗料が最適解 一条工務店の住宅は、デザイン性と性能を兼ね備えた優れた住まいですが、外壁塗装を行う際は塗料選びと施工技術が非常に重要です。艶を抑えた落ち着きのある仕上がりを求めるなら、スーパーセランG4による艶消し無機塗料塗装がおすすめです。 岡崎市で外壁塗装を検討中の方は、火災保険の申請サポートにも対応している愛知建装にご相談ください。 愛知建装なら、 一級塗装技能士による高品質な外壁塗装工事 スーパーセランG4で長期間美観を維持 艶消し仕上げで一条工務店住宅のデザイン性を引き立てる 火災保険の申請で修繕費を軽減 無料見積もりで安心・納得の提案 地域密着・高品質施工の愛知建装が、あなたの大切なお住まいを長く美しく守ります。 関連記事リンク 外壁塗装と屋根カバー工法を愛知建装で同時に施工する利点とは 愛知建装が無機塗料でアパートの外壁塗装を施工するメリットとは 愛知建装が足場無料期間のキャンペーン中に無料見積もりを取るメリットとは? 外壁塗装のダブルトーン工法はなぜ選ばれるのか ✅ この記事のポイントまとめ 一条工務店住宅には艶消し塗料が最適 スーパーセランG4で長期耐久・高級感のある仕上がり 一級塗装技能士による高品質施工で安心 火災保険の申請サポートで修繕費を軽減 無料見積もりで現状を正確に診断 岡崎市の外壁塗装専門店、愛知建装へのお問い合わせはこちらから!! 岡崎市地域密着の外壁塗装専門店の愛知建装自慢の施工実績はこちらから!! 岡崎市の外壁塗装専門店の愛知建装がいただいたお客様の声はこちらから!! 豊明市・大府市・名古屋市・東郷町・岡崎市・豊田市・刈谷市・知立市・安城市・みよし市・日進市・幸田町の外壁塗装・屋根塗装・コーキング工事・板金工事・防水工事・左官工事は愛知建装へ!
2025.11.13(Thu)
詳しくはこちら