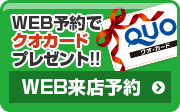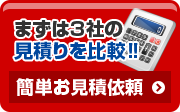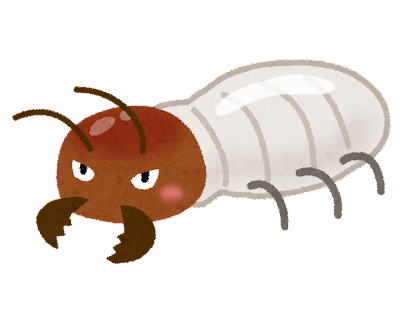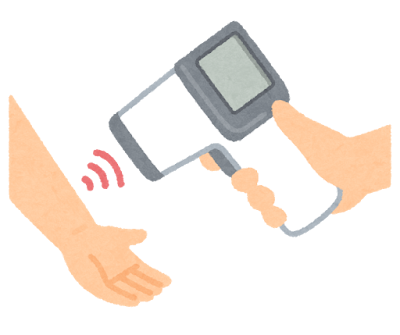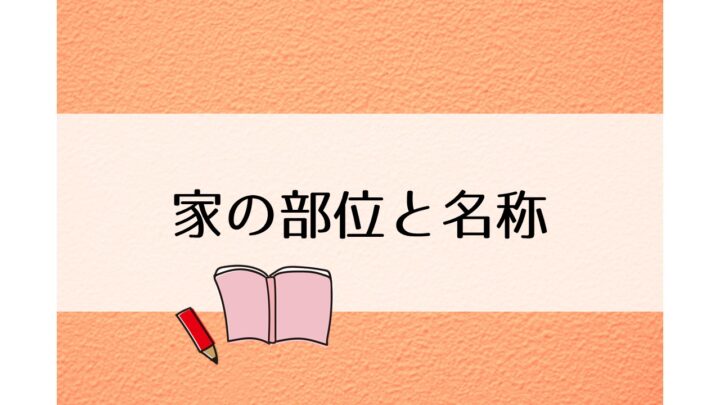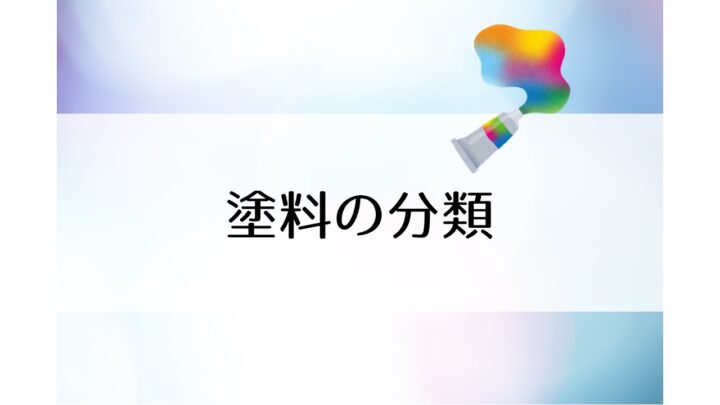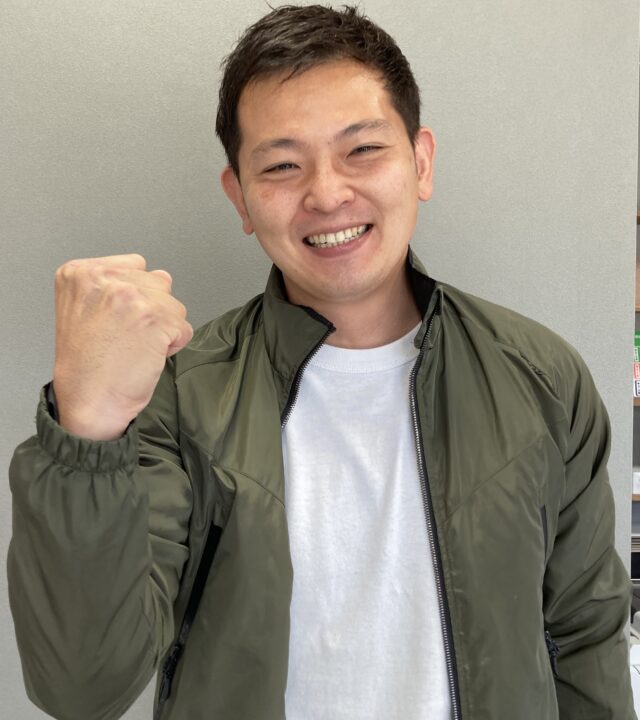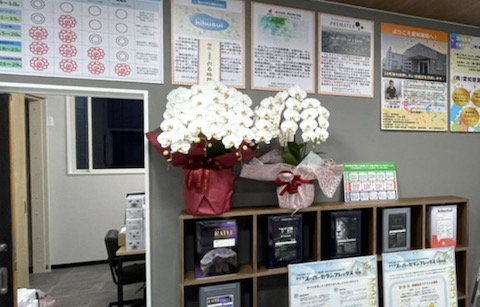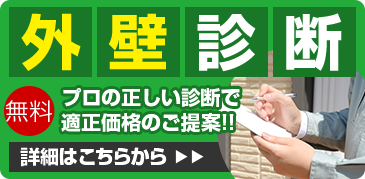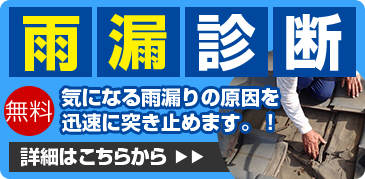【大府市・豊明市】塗装の工程で大切なポイント|外壁塗装・屋根塗装&雨漏り専門店の愛知建装
大府市・豊明市の皆様、こんにちは! 大府市・豊明市の外壁塗装・屋根塗装・防水工事専門の愛知建装です。本日も元気に頑張ります!よろしくお願いします(*´ω`*) 今回は【塗装の工程で大切なポイント】 についてお話していきます★ はじめに 外壁塗装を行う機会は少ないと思います(`・ω・´) なにをするのか何に気をつければよいのか、 分からないことも多いかと思います。 外壁塗装の重要ポイントを解説していきます★ 外壁塗装・屋根塗装の工程 工 程 内 容 塗装の準備 必要な材料の搬入や、ご近所の方への挨拶回り 足場の設置 外壁塗装や屋根塗装に必要な足場の設置 高圧洗浄 外壁・屋根表面の汚れを落とす 養生シート 窓のサッシや車などへの塗料の付着、その他の事故を防ぐ 下地処理 下記の施工を行う ケレン作業(金属部分のサビを落とす) コンクリート・モルタル部分の補修 外壁・屋根のひび割れの補修 塗膜の剥がれの補修 塗装 下塗り:外壁・屋根の凸凹を調整し、その後の工程がスムーズに 中塗り:下塗りが乾いたら行う 上塗り:中塗りと同じ塗料を塗り、塗膜を強くする 点検 工程の点検と手直し 足場解体・片付け 足場の解体と破棄物の片づけ 外壁塗装の工程で大切なポイント 高圧洗浄・下地処理で塗料が付着しやすくなる為、高圧洗浄・下地処理・塗装は特に重要な工程です! どの工程を欠いても、塗料の耐久性などに影響を与えます。 高圧洗浄 高圧洗浄は長年のホコリや汚れを落とし、塗料の密着性を高め塗料の浮きや剥がれを防ぎ、美しい外壁を長続きさせるために行います(`・ω・´)✨ 下地処理 下地処理では、ケレンやひび割れの補修などを行います。 雨漏りやサビが広がり、外壁や屋根の劣化を早めないため下地処理を正しく行うことで表面が整い、塗料が付着しやすい状況を作ることができます! 3度塗り 塗装は、下塗り⇒中塗り⇒上塗りの3度塗りで塗装することで耐久性が高まります!!!! 3度塗る事で初めて塗膜の効果が発揮され、紫外線や雨風などの過酷な環境に耐えられます★ 塗装の回数を減らすと耐久性が劣る為、頻繁に外壁塗装や屋根塗装を行う必要性が出てきます。愛知建装は、丁寧に塗装工事を行います(`・ω・´) 外壁塗装や屋根塗装の工事中に気を付けるポイント 洗濯物は外干ししない 工事期間中は、汚れや塗料が付いてしまうので洗濯物を外干しできません。 工事期間が予定より遅れる事も想定する 外壁塗装や屋根塗装の工事は気候天候に左右されます。打ち合わせで提示される工事スケジュールはあくまでも目安で、工期が遅れることを想定しておきましょう! 最後に 塗装の準備では、外壁塗装は大きなトラックが出入りするため、ご近所の方の理解が必要です!そのため、愛知建装ではご近所様への挨拶回りを徹底しております。 また、足場の解体の片付けでは、解体作業中に外壁にキズが付き塗装が剥がれる場合などがあります…最後にもう一度外壁全体をチェックするように心がけましょう★ ★ 無料お見積もりはこちらから ★ ご相談・お見積り・診断・カラーシミュレーション 無料で承っております! 外壁塗装・屋根塗装をお考えの方、 外壁塗装についてお困りの方は お気軽に愛知建装にお問い合わせください♪ ☆ 外壁塗装・屋根塗装やその他の施工事例はこちらから ☆ 愛知建装は外壁塗装・屋根塗装・防水工事以外の工事でも、瓦屋根の漆喰工事・コーキング工事・板金工事などの工事を安心・安全・お値打ち価格にて承っております!! ただ単純に外壁塗装工事だけではなく、ひと手間を惜しむ業者さんがほとんどの昨今、愛知建装では長く持たせるためのひと手間を惜しみません!! お客様の『ありがとう!』が私たちのエネルギーです! しつこい営業は一切なし!無料お見積もりはこちら!! それ以外のことでも当社では経験豊富な専任スタッフによる、的確かつ丁寧な説明でお客様にご安心頂ける提案をしております。 お客様の利益のために、安心・安全を心がけて日々精進して参ります!! 些細なことでも外壁塗装・屋根塗装・防水工事に関しましては専門業者である愛知建装へお任せください! 大府市・豊明市地域密着の外壁塗装専門店、愛知建装へのお問い合わせはこちらから!! 大府市・豊明市地域密着の外壁塗装専門店の愛知建装自慢の施工実績はこちらから!! 大府市・豊明市地域密着の外壁塗装専門店の愛知建装がいただいたお客様の声はこちらから!! 大府市と豊明市でクチコミ高評価で施工実績が豊富な愛知建装に聞く!外壁塗装工事で重要視すべきとは? はじめに|外壁塗装で「本当に大切なこと」を理解していますか? 大府市・豊明市で外壁塗装を検討している方から、愛知建装には次のような声が多く寄せられます。 「結局、何を一番重視すればいいの?」 「塗料?価格?業者?」 「情報が多すぎて分からなくなった」 「失敗しない判断基準を知りたい」 外壁塗装について調べれば調べるほど、 塗料の種類 工事内容 相場 業者比較 など情報が溢れ、何を基準に決めればいいのか分からなくなる方が非常に多いのが現実です。 そこで今回は、大府市・豊明市でクチコミ高評価、施工実績が豊富な外壁塗装専門店「愛知建装」に、「外壁塗装工事で本当に重要視すべきことは何か?」をテーマに、数多くの施工経験・失敗例・お客様の声を踏まえて、プロの本音を徹底的に聞きました。 結論|外壁塗装で重要視すべきなのは「目に見えない部分」 まず結論からお伝えします。 外壁塗装工事で最も重要視すべきなのは、完成後には見えなくなる「下地・工程・管理」です。 どんな塗料を使うか いくらで工事するか も大切ですが、それ以上に、 正しい診断 適切な下地処理 丁寧な施工管理 信頼できる業者 これらが揃っていなければ、どんなに高級な塗料を使っても、良い外壁塗装にはなりません。 なぜ外壁塗装は「完成後」に失敗が分かりにくいのか? 理由① 見た目は最初きれいに仕上がるから 外壁塗装の怖いところは、 手抜き工事でも 初期不良があっても 完成直後はきれいに見えてしまうことです。 しかし数年後、 塗膜の剥がれ ひび割れ 色あせ 雨漏り といった形で、問題が表面化します。 理由② 一度塗ると「やり直し」が難しい 外壁塗装は、 上塗りを剥がす 下地からやり直す という作業が非常に大変で、失敗すると修正費用が高額になりやすい工事です。 外壁塗装工事で重要視すべき10のポイント【完全版】 ここからは、外壁塗装工事で絶対に重要視すべきポイントを、優先順位の高い順に詳しく解説します。 ① 正確で丁寧な「現地調査・劣化診断」 なぜ最重要なのか? 外壁塗装は、 建物の状態 劣化の進行度 環境条件 によって、最適な工事内容がまったく異なります。 現地調査が甘いと、 不要な工事をされる 必要な補修が抜ける といった問題が起こります。 正確に外壁塗装の見積書を作成するための現地調査とは?https://aichikensou.jp/blog/genchi-chousa ② 下地処理の内容と質 外壁塗装は「下地で8割決まる」 高圧洗浄 ひび割れ補修 コーキング処理 錆止め処理 これらの下地処理を省略すると、塗料本来の性能は発揮されません。 外壁塗装の劣化症状とは?https://aichikensou.jp/blog/deterioration ③ 塗装工程(塗布回数・乾燥時間) 3回塗りは「基本中の基本」 下塗り 中塗り 上塗り それぞれに適切な乾燥時間が必要です。 工程を短縮すると、 塗膜不良 剥がれ 耐久性低下 につながります。 ④ 塗料の種類より「適材適所」 高耐久塗料=正解ではありません。 外壁材との相性 建物の状態 今後の住まい方 に合っていない塗料は、オーバースペックや無駄なコストになります。 外壁塗装で使用される塗料の種類とは?https://aichikensou.jp/blog/paint-types ⑤ 見積書の内容が明確かどうか 重要なのは「金額」ではなく「中身」です。 チェックすべきポイント 工程ごとの記載があるか 塗料名・メーカー名が書かれているか 「一式」表記が多すぎないか ⑥ 業者の施工管理体制 誰が工事を管理するのか 職人任せになっていないか 問題が起きたときの対応体制 管理が弱い工事ほど、品質にムラが出ます。 ⑦ 工事中の説明・コミュニケーション 外壁塗装は、お客様が不安を感じやすい工事です。 今日の作業内容 明日の予定 注意点 を説明してくれるかどうかで、満足度は大きく変わります。 外壁塗装工事中のお客様の過ごし方は?https://aichikensou.jp/blog/during-construction ⑧ 近隣への配慮・マナー 外壁塗装は、 足場 騒音 塗料臭 など、近隣に影響が出る工事です。 事前挨拶 養生 清掃 を重視する業者かどうかは重要です。 ⑨ 工事後の保証・アフターサポート 外壁塗装は、工事が終わってからが本当のスタートです。 保証内容 保証年数 定期点検の有無 を必ず確認しましょう。 ⑩ 「この会社なら任せられる」と思えるか 最終的に重要なのは、 質問しやすい 正直に話してくれる 不安を解消してくれる という人としての信頼感です。 大府市・豊明市で特に重視すべき理由 大府市・豊明市は、 住宅密集地が多い 湿気・結露の影響を受けやすい 日陰面の劣化が進みやすい という地域特性があります。 工事施工中の外壁塗装に結露が与える影響とは?https://aichikensou.jp/blog/condensation 地域を理解している業者でなければ、適切な判断はできません。 愛知建装が「重要視すべき点」を徹底している理由 理由① 完成後に後悔させたくない 「見えない部分」を最も大切にしています。 理由② クチコミがすべての評価になる 地域密着だからこそ、手抜きができません。 理由③ 長期的な視点で工事を考えている 「10年後も安心」を基準にしています。 愛知建装で外壁塗装工事をするメリットとは?https://aichikensou.jp/blog/aichikensou-merit よくある質問 Q. 一番重視すべきポイントは何ですか?A. 現地調査と下地処理です。 Q. 高い塗料を選べば安心ですか?A. 建物に合っていなければ意味がありません。 Q. 安い業者は危険ですか?A. 安さの理由を必ず確認しましょう。 まとめ|外壁塗装は「見えない価値」を見極める工事 外壁塗装工事で重要視すべきことは、 見積金額 塗料のグレード だけではありません。 正確な診断 丁寧な下地処理 誠実な施工管理 信頼できる業者選び これらを重視することで、本当に満足できる外壁塗装が実現します。 大府市・豊明市で、 外壁塗装を検討中 何を基準に選べばいいか迷っている 失敗したくない という方は、クチコミ高評価・施工実績が豊富な愛知建装にぜひご相談ください。 外壁塗装は、「何を重視するか」で結果が決まる工事です。 豊明市・大府市・名古屋市・東郷町・岡崎市・豊田市・刈谷市・知立市・安城市・みよし市・日進市・幸田町の外壁塗装・屋根塗装・コーキング工事・板金工事・防水工事・左官工事は愛知建装へに
2026.01.08(Thu)
詳しくはこちら